家に出るクロゴキブリ、お店で増えるチャバネゴキブリ
取材現場の古民家へと移動する〈HOKUROKU〉取材班とダスキンの皆さん
前書き
古民家におけるゴキブリ対策を学ぶ今回の取材は実際の古民家を利用して行われました。
しかも、一般住宅として使われる古民家と飲食店など商業利用される古民家では対策も異なってくると事前打ち合わせで知ります。
そこで、北陸某所の古民家住宅(リフォーム前)と、古民家をリノベーションした飲食店の2カ所で行われました。
 インタビューが行われた古民家1階の茶の間。窓の外に中庭が見える
インタビューが行われた古民家1階の茶の間。窓の外に中庭が見える
それにしても「ロケ場所」探しは大変でした。扱う内容から個人住宅のオーナーも飲食店のオーナーもなかなか協力してくれなかったわけです。
しかし、前者の一般住宅については場所の特定が行われない形で利用を認めてくれた勇気あるオーナーと出会いました。
後者の飲食店については〈HOKUROKU〉プロデューサーである明石博之がオーナーを務める富山県射水市の人気カフェ〈cafe uchikawa 六角堂〉の利用が認められました。
明石いわく、cafe uchikawa 六角堂は工事の段階からミリ単位でゴキブリの侵入経路をふさいだそう。オープン後のゴキブリ対策も徹底していると言います。
対策には自信がある上にプロの人にチェックしてもらえればお店にとってもプラスだとロケ地としての利用を認めてくれました。
古民家をリノベーションして生まれた〈cafe uchikawa 六角堂〉。年間2万人が訪れる人気のカフェ
プロデューサーの責務なのかもしれませんが、HOKUROKUの取材にためらいもなく場を提供してくれた明石博之には身内ながらあらためて感謝を表明します。
北陸某所の一般住宅の古民家(リノベーション前)で取材はまず行われ、富山県射水市にあるcafe uchikawa 六角堂(古民家をリノベーションした建物)で次に行われました。
「彼を知り己を知れば百戦殆(あやう)からず」の孫子の言葉どおり、ゴキブリの生態を学ぶところから始まって、古民家を住居・飲食店として使う際の注意点に話は及びます。
目次ページでも書いたように文中には1匹もゴキブリの写真は登場しません。最後まで安心して読んでくださいね。
飲食店は「チャバネ」に注意
―― はじめまして。HOKUROKU編集長の坂本正敬と申します。
プロデューサーである明石博之と副編集長の大坪史弥も取材現場に今日は同席させてもらっています。
特に、明石は、これまで古民家のリノベーションを手掛け、さまざまな商業施設をプロデュースしてきた立場です。
個人的に聞きたい話がいっぱいあるそうですので、インタビューの途中に横入りするかもしれませんがお願いします。
話を聞かせてもらう今日の「先生」は、株式会社ダスキン高岡のケアサービス事業部に所属する瀧川祐市さんです。
ダスキン高岡の支店長、さらにダスキン本部の方にも来てもらっています。
左(手前)からHOKUROKUプロデューサーの明石博之、株式会社ダスキンの笠原大輔さん、編集長の坂本正敬、株式会社ダスキン高岡の瀧川祐市さん
皆さんのスケジュールを考慮しながら取材場所を選定し、日程調整する作業の苦労はなかなかでした。
内容が内容だけに取材場所が二転三転してしまったからです。
貴重な話が聞けると思って今日は楽しみにしています。瀧川さん、よろしくお願いします。
瀧川:よろしくお願いします。
―― 企画の意図を最初に整理させてください。
個人的な話になりますが、京都にある長屋タイプの古民家に暮らす知人と前に話していた時、古民家暮らしはゴキブリとの同居状態だと知りました。
古民家と言えばリノベーションしてカフェにしたり宿にしたりする物件として人気ですよね。
古民家をリノベーションして商業施設や住居として使っている人を北陸でもたくさん見ます。
私の大好きな北陸のカフェの多くは、そうした古民家をリノベーションしたお店だったりします。
ここにいるHOKUROKUプロデューサーの明石博之も北陸の古民家を500件以上今までに内見し、カフェにしたり・宿にしたり・バーにしたり・オフィスにしたりと、リノベーション工事をしてきたプロフェッショナルでもあります。
「古民家のリノベの物件ってゴキブリって出るの?」とその明石に聞くと、「出るどころか、しっかり対応しなければ経営に差し支える」と言われ、びっくりしてしまいました。
古民家をリノベーションした商業施設は工事の段階でいろいろ奇麗にしているから、ゴキブリやネズミなどネガティブな害虫獣とは無縁だろうと、個人的なイメージとして勝手に考えていたのです。
ダスキン高岡の瀧川祐市さん
私と同じイメージを持つ利用者は少なくないはずです。古民家の宿泊施設でゴキブリが発生したためにインターネット上で低評価を付けられたという事業者を実際に知っています。
この利用者の思い込みは本当に身勝手で「どこまで潔癖なんだ」と自分自身にも突っ込みを入れたくなるのですが、経営者にとっては一方で無視できない期待値だと思います。
北陸3県を舞台とするウェブメディアHOKUROKUのミッションは「北陸の暮らしを豊かにする」です。
その豊かさの中には楽しさも含まれていて、「休日のお出かけ先に困らない世の中づくり」もその楽しさの中には含まれているわけです。
愛される場所づくりや次のお店のつくり方など、商業施設をオープンしたい経営者たちに役立つ情報も、私たちの媒体では過去に届けてきました。
関連:「人が集まる場所」のつくり方をGNLの明石さん・BnCの山川夫妻と考える
すてきなお店を北陸でつくりたいと願う経営者たちが、近い将来に直面するであろうゴキブリ問題に先回りして何か有効な情報を出せないか、そう考えて今回の特集を企画しました。
そこで今日は、お掃除会社として暮らしや働く環境の衛生管理を総合的にサポートし、害虫獣の駆除も行うダスキンの皆さんに、実際の古民家まで来ていただいたわけです。
取材の流れとしては古民家に住み着くゴキブリの概論をまず教えてもらいます。
古民家をリノベーションした後に住居として利用したい、あるいは商業施設として利用したい読者向けの情報をその上で教えてもらえればと思います。
瀧川:分かりました。
―― それでは、古民家に暮らすゴキブリの概論から質問させてください。
日本に何種類かゴキブリは存在しているものの一般住宅と飲食店で見かけるゴキブリは種類が限られていると聞きました。
ゴキブリの生態が解説されたダスキンの資料
瀧川:そのとおりです。日本に生息しているゴキブリは細かく言うと40種類くらいいるのですが、建物に入ってきて問題になるゴキブリは4種類1です。
北陸など気温が比較的低い地域ではチャバネゴキブリとクロゴキブリがその中でも問題になってきます。
―― チャバネゴキブリとクロゴキブリの違いは何でしょうか?
瀧川:見た目の違いは名前のとおり、黒く大きなゴキブリがクロゴキブリです。一般家庭で見るほとんどのゴキブリがこれです。
飲食店に住み着くゴキブリはチャバネゴキブリが多く、小さくて名前のとおり茶色い見た目です。
一般的にマンホールの下などの外にクロゴキブリは暮らしていて、食べ物などを求めて家の中に入ってきます。
飲食店にある冷蔵庫や食器洗い機といった電気製品のモーター付近など熱源を一方のチャバネゴキブリは好み、店内に住み着いて繁殖します。
えさとなる食べ物や水が豊富にあるだけでなく、暖かい場所を好むチャバネゴキブリにとって、什器のモーター部分などに熱源もある飲食店は最高の環境です。
また、両者の違いとして繁殖力の強さが挙げられます。クロゴキブリよりもチャバネゴキブリの方が繁殖力は強く、卵しょう(卵の入ったさや)から30~40匹の幼虫が生まれ、2カ月ほどで成虫になると言われています。
クロゴキブリの卵が近くにあったら食べてしまうくらい繁殖力が強いのでチャバネゴキブリに飲食店は注意したいです。
数ミリのすき間があれば侵入が可能
取材が行われた古民家の布基礎の部分
―― チャバネゴキブリとクロゴキブリは、どうやって家の中へやってくるのでしょうか?
瀧川:クロゴキブリとチャバネゴキブリを比較した場合、飛べるゴキブリはクロゴキブリだけです。
クロゴキブリはそのために活動範囲が広く、よそから家の近くにやってきて、すき間を見つけては家の中に入り込んできます。
「ゴキブリを1匹見つけたら他に何十匹もいる」といった話をよく聞きますよね。
チャバネゴキブリの場合には当てはまるのですが、クロゴキブリの場合はそうとも限りません。例えばクロゴキブリが1匹で外から飛んできて、すき間を見つけて家の中に入ってきただけとなれば、他にはまだいない可能性も考えられます。
それだけ行動範囲が広く動き回っているとも言い換えられます。
―― すき間とは、どの程度のすき間でしょうか?
瀧川:数ミリのすき間があればゴキブリは侵入が簡単に可能です。
今回の話で言えば、どうしても古民家はすき間が多くなります。基礎にしてもべた基礎2ではなく布基礎3が基本です。
その意味で、家の下から入り込んでくる侵入経路が考えられます。
―― べた基礎と布基礎について整理させてください。明石から教えてもらった話ですが、住宅の底面を全て鉄筋コンクリートで覆ってしまう土台のつくり方がべた基礎ですね。
一方の布基礎は、本当に布を使うわけではありませんが、建物の骨格部分に沿って「┴」字型の断面をした鉄筋コンクリート造の土台をつくるだけなので、建物の下の地面はむき出しの状態になります。
「古民家=すき間風・寒い」というイメージがあるように、老朽化した住宅は基礎から床にかけてすき間が目立つ場合もあります。クロゴキブリが入り込む余地がたくさんあるという話ですね。
チャバネゴキブリに関してはどうでしょうか?
瀧川:お店に定住するチャバネゴキブリがよそから侵入してくる場合、ゴキブリの卵が納入品に付いているケースが考えられます。
ビールケースだとか飲食物が入った段ボールだとか。
こうした入れ物に卵が付着していて知らずにお店の中に入れてしまい繁殖するリスクが考えられます。
―― お店側の対策として何をすればいいのでしょうか?
瀧川:少なくとも納入時に利用したケースや段ボールを放置しないですぐに処分・外に出すといいです。
段ボールにしてもプラスチックの箱やかごが安く売っています。
段ボールで商品を納入したら中身をすぐに自前のケースに移して、外から持ち込んだ段ボールは処分する作業を徹底してもらえればと思います。
(大坪副編集長のコメント:ダンボールの処理はお店に関わらず一般家庭でも後回しにしがちではないでしょうか。
私もため込んだダンボールを取材後すぐに捨てに行きました。
それにしてもゴキブリはなぜ人の家に入ってくるのでしょう? 根源的な質問に次の回ではGメンが答えます。)
2 住宅の基礎の1つ。建物の底面全体に鉄筋コンクリートの土台をすき間なく設ける。布基礎と比較した場合、建物の底面全体が鉄筋コンクリートで覆われるため、地面からの害虫の侵入が防げる。
3 木造建物の骨格部分の下に設けられる┴字型の断面をした鉄筋コンクリート造の土台。一戸建て住宅で最も普及しているが建物の下の地面はむき出しになる、基礎の部分に害虫が侵入できる。









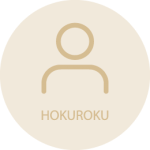






オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。