線引きのあいまいさを取り入れながら文化が回る
―― 工芸を見る際のポイントをここまで教えてもらいました。
しかし、工芸とは辞書を調べると「美的価値を備えた実用品をつくる営み」と書かれています。
その意味から考えれば実用品ですよね。
先ほどから職人の工芸ではなく作家の工芸を前提とした話が中心だったため「見る」楽しみ方が優先されてきたと思うのですが、使う楽しみは工芸にないのでしょうか?
唐澤:もちろんあります。例えば、桃山時代とか江戸時代の初期につくられた器が今すごくいいと言われています。
自分が企画している備前焼の展覧会では桃山時代から江戸初期の器が展示されていますが、ほとんどが現役です。
300年・400年と長い時間を大切に使われてきた器はその分だけの何かが乗っかっているのですよね。
作品展で器をお借りする場面でも、すごく大切に使われてきた器と、買ってから一度も使われていない、箱からぽこんと出された器では、味わいが全然違います。
後者は、ちょっとかわいそうと思う時すらあります。
―― 使われてこそなんぼの部分もやはり工芸品にはあるのですね。
唐澤:愛知の美術館で働いた時に館の茶室で使う器をある作家さんから買いました。
何年かして、その作家さんが自分の器を使って茶室でお茶を飲んだ時、あまりにも変化が良かったので「茶室の器を新しい器と交換してくれないか?」と言ってきたことがあります。
お寺さんの持っている国宝のお茶わんを借りた時も住職の方が一度使って一番いい状態で貸してくださいました。
展覧会の途中も「お茶会があるから一回戻してね」だとか、借りに行った時に茶入れにお茶が残っていただとか。
代々受け継いできた工芸品を次の代へ受け継がせるために大切に使い続けている人たちが世の中には確実に存在しています。
大切にされた器を逆に1週間・2週間と展示すると器が乾いてしまってどこかかわいそうな感じに見えてきます。
―― ただ、その話を突き詰めて考えると国立工芸館のようにたくさんの工芸作品を収蔵して展示するやり方は矛盾していませんか?
国立工芸館にもストックがいっぱいあるはずで、寂しげに眠っている「子たち」もたくさん居るはずです。
唐澤:居ますよね。なかなか収蔵品に関しては使えないと思います。使いたいけれど使えない。
国民の財産ですから粗相があってはいけません。
再掲。橋本真之〈果樹園―果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実〉(1978ー88年)
ただ、つくる側も作品が完成した瞬間だけではなく、半年後・1年後に変わる姿を想定しているはずです。
それを計算に入れると展示している側も見る側も新しい楽しみ方が出てくると思います。
―― それはとても面白い考え方だと思うのですが、職人と違って作家は自分の工芸品を使ってもらわなくてもいいと、そもそもの話として考えているのでしょうか?
唐澤:両方だと思います。使ってほしい、見て楽しんでもらいたい、その両方です。
「見る=使う」と考える鑑賞者たちも存在しているわけですから。
―― それはかなり高度な人たちの楽しみ方ではないですか?
唐澤:そんなことはないと思います。例えば、飾りつぼがあります。
この工芸品の用途は「飾る」です。空間の中で物として生きる工芸品、つまり「飾る」が用途なのです。
―― なるほど。「飾る」が実用なのですね。
唐澤:そもそもの話として、作家の顔が見える作品を国立工芸館は収蔵しています。
実用品としての工芸品を選んでも他と同じ工芸品が前後の時代にたくさん存在しているわけです。
類似品がたくさんあれば古い方が価値を持つので新しい工芸品は自然に淘汰されてしまいます。
新しい工芸品を残して次の時代・次の世代に引き継いでいかないと継承が途切れてしまいます。
だからこそ顔の見える、他に類例のない、時代を取り込んだ新しい作家の作品を収蔵し、後世に引き継いでいこうとしています。
その前提に立った上で、先ほどの使う・使えないの問題に戻ると、国立工芸館で展示・収蔵しているだけでも、工芸品の見え方には変化が生まれるので楽しみは深まると考えています。
線を引かない分だけいろいろな人が入ってこられる
―― お茶会の器の話が先ほどありました。ちょっと立ち止まって素朴な質問をさせてもらいたいのですが、よく聞く2つの言葉、工芸と民芸の違いは何なのですか? きっと長く議論されている話題だと思うのですが。
工芸品を辞書で調べると「美的価値を備えた実用品」と書かれています。民芸品を辞書で調べると「地方色豊かな手工芸品」と一方で書かれています。
個人的な感想で言えば「工芸品」の言葉には洗練された美の響きがあって、「民芸品」には地べたに近い生活感が感じられます。そもそも「民」の言葉自体が支配下に置かれる人々を意味する言葉ですから。
とはいえ、先ほどの茶室やお茶会の器の話題に戻ると、作家の名前はないけれど地方色豊かな手工芸品(民芸品)が長い時間を掛けて、他にない価値を帯び始めるケースもあるのではないかと無学な私は思います。
言い換えれば、茶室で長らく愛用されながら美術館に貸し出されるくらいの器の中には、工芸品だけでなく民芸品もあるのではないのかなと。
唐澤:結論から言うと、工芸と民芸の違いはあいまいです。つくる側はある程度線引きしているのですが、われわれ鑑賞者にとって線引きは難しいと思います。
民芸の人たちは名もない、むしろ名前をあえて記さないで素晴らしい仕事をしています。
場合によってその意識は作家の工芸に迫るかもしれません。そうなるといよいよ境界があいまいになってきています。この問題はずっと昔から言われてきました。
しかし、そのあいまいさを日本はうまく利用していると思います。ばしっと線を引かないと言いますか。
美術の場合は線を引いてしまいますよね。外国でも例えば、ceramic artist(陶芸作家)と名乗るかpotter(陶工)と名乗るか線引きにすごくこだわります。
九谷焼。写真提供:石川県観光連盟
日本の工芸の場合は逆に、線を引かない分だけいろいろなジャンルの人が入ってこられる自由があります。
例えば、現代美術の人が工芸の素材とか技法だとかを見て「これは面白い」といい部分を吸収していきます。
工芸の内側に居る人たちでも機能性・デザインに特化して自分の作品を絞り込んでもいけるし、表現に特化した作品づくりも展開できます。
そうした自由な楽しみ方がつくる側にはあるし、その自由な感じを受け手も膨らませながら、見ても使っても楽しめる幅広さが工芸にはあります。
―― それが日本の工芸なのですね。
唐澤:そもそも「工芸」の言葉自体も明治時代に生まれた新しい言葉です。
それ以前の江戸時代にさかのぼれば生活の中に美術があって境界はありませんでした。
江戸時代のころからこの北陸は工芸が特に強い地域なので、境界線がいい意味であいまいです。
そのあいまいさの中で石川(金沢)の文化は上手に回っていると思います。こちらに来てすごく感じた文化的な特徴です。
―― 境界があいまいで、線を引かない分だけいろいろなジャンルの人が入ってこられる自由さの話、すごく面白いですね。だから、工芸かいわいにはこのところ、なんだか面白そうな取り組みが目立つのかもしれません。
工芸というと「本物」とか「正当」とか「伝承」とか、ちょっと一般の人にはとっつきにくい部分もある気がします。
しかし、そういった世界観とは異なる新しさ・面白さを玄関口に、工芸の楽しさや素晴らしさを身近に感じさせてくれる仕掛け人たちが北陸でも目立つ気がします。
境界線があいまいで自由に出入りできる懐の深さが日本の工芸の世界にはあって、今の工芸の世界をその寛容さが面白くしているのだと唐澤さんの言葉で理解できました。
(副編集長のコメント:線引きのあいまいさが民芸や工芸や美術の垣根を低くし、結果として、それぞれの文化が刺激を受け合い、育まれている。日本らしい話ですね。
こうした工芸の基礎知識を持った上でどこの産地に出掛ければいいのか、マイクロツーリズムの行き先の話に次は続きます。)
6純白の磁器。







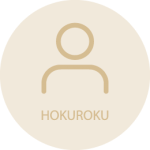







オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。