「どこのタンブラー?」と質問される気持ち良さ
土直漆器(鯖江市)の〈URUSHI MOBILE TUMBLER〉
福井ロフトなどを見学していると福井県の鯖江市に人気のタンブラーを手掛ける会社があると情報が入ってきました。
福井の鯖江と言えばメガネで有名ですが、鯖江には越前漆器11など伝統工芸の産地が集積しています。コーヒー・タンブラーづくりにその伝統技術を生かした土直漆器(鯖江市)の〈URUSHI MOBILE TUMBLER〉があると知りました。
公式ホームページで最初に見た時に「こういうタンブラーを探していた」と思いました。編集部に情報をシェアしても「これなら持ちたい」と気持ちの良いリアクションが返ってきます。
プロダクトとして持ちたいかどうかが大事だとすればURUSHI MOBILE TUMBLERは写真の段階で成功しています。
鯖江市の様子
同製品を立ち上げた土直漆器の土田直東さんにも会いに行きました。
取材当日の鯖江は曇り。近所の山からは水蒸気が立ち上っています。湿度が高いほど漆は固まりやすくなるため産地としては湿度の高さが大事みたいです。
産地として越前漆器は日本最古の1500年近い歴史があるそう。その産地の中でも土直漆器は歴史の若い会社だと2代目社長の土田直東さんが教えてくれました。
土田直東さん
URUSHI MOBILE TUMBLERをリリースする土田直東さんは世界的な大手レコードショップの社員として東京で働いた後、父親の仕事を継ぐために鯖江へUターンした人です。
「外の世界を知る私のような経営者がどんどんチャレンジして漆器の世界に対する憧れを若い人に持ってもらいたい」
との願いもあって、URUSHI MOBILE TUMBLERづくりを始めたのだとか。
慶応義塾大学のメディアデザイン研究科から伝統の技術を生かして海外へ物を売っていきたいと鯖江市に声が掛かったところからプロダクトの開発が始まります。
さまざまな課題を産地として抱えていた同市の越前漆器が手を挙げ、クラウドファンディングを経て商品化に至りました。
飽和状態のタンブラー業界で「違い」を実現
 カメイ・プロアクト社(東京都)の〈Thurmo mug〉に土直漆器が伝統の技術で漆を塗る。色彩は経年変化して深みを増す
カメイ・プロアクト社(東京都)の〈Thurmo mug〉に土直漆器が伝統の技術で漆を塗る。色彩は経年変化して深みを増す
北陸の風土に似合うタンブラーとしてURUSHI MOBILE TUMBLERは1つの理想的な形を示した商品なのかもしれません。
真空二重構造のタンブラーに漆塗りを用いた製品は、飽和状態のタンブラー業界の中で差別化を見事に実現しています。
〈スターバックスコーヒー〉などにユーザーが持ち込むと店員から「どこのタンブラーですか?」と質問を受けるそう。使っている本人としてこの質問はうれしいですよね。
何気ないやり取りがきっかけで店員との会話も弾み、使っている人のステイタスにもなって、満足度にも直結しているみたいです。
価格帯は1万円前後12と決して安くありません。それでも月に500~600個、年間で7,000~8,000個のペースで売れていると言います。
海外の人に向けて当初は売り出す予定だったそうですが、都市部に暮らす30~40代の日本人に意外にも今は売れているみたいです。
贈答用としても好まれていて、企業が自社のネームを入れイベントでギフトにするニーズもあると土田さんは言います。
デザインやコンセプトが購買や贈答の原動力になっている、見本となるような商品が北陸3県にもあると分かりました。
コーヒー専用の容器として考えてみる
土直漆器。URUSHI MOBILE TUMBLERはこの建物の中でも販売される。都内や関西のショップ、Thurmo mugのルートでも取り扱われている
ただし、URUSHI MOBILE TUMBLERはコーヒー専用のタンブラーとして用途が限定されているわけではありません。
このタンブラーで土田さんは毎日お酒を飲んでいると言います。真空二重構造のため氷が溶けにくくお酒がおいしく飲めるのだとか。
しかし、今回の特集テーマにあえて寄せて、コーヒー専用の容器としてURUSHI MOBILE TUMBLERを見た時、真空二重構造の高い保温機能が裏目に出る可能性もあるはずです。
コーヒーを水筒に入れて持ち運んだ結果、酸味や雑味が増してしまった経験はありませんか? 高い温度で長時間保管したコーヒーは雑味や嫌な酸味が増すと知られています。
価格的に1万円前後の値段設定も日常的な利用をイメージした場合、ちょっと高すぎるハードルもあるはずです。
容器としての背の高さも、スクリュー式のふたについても、コーヒー専用の用途に限って見れば、商品選びの際に注意が必要かもしれません。
〈KeepCup〉の場合は現場に立つバリスタが開発した経緯もあって、カフェのカウンター内でストレスなく使えるように、エスプレッソ・マシンの抽出口に直接セットできるサイズ感を意識しています。
混雑時のバリスタの手間を考え、容器のふたもねじ込み式ではなく、押してはめるタイプが意図して選ばれています。
思わず手に取りたくなるデザインが大前提にあって、バリスタにも使い勝手のいい機能を持っている。コーヒー・タンブラーのある暮らしを北陸3県で広める鍵を、コーヒー専用の容器として計算された細部こそが一方で握っているのではないかと思いました。
とりあえず調査編(始まりのメルボルン編)はこれで以上です。まだまだ研究は続きますので、気長に続編を待っていてくださいね。
(副編集長のコメント:いろいろ調べて考えた結果、HOKUROKUオリジナルのドリンク容器づくりに最終的には展開したりするんですかね。時期については未定ですが続きを楽しみにしてください。)
文:坂本正敬
写真:山本哲朗
編集:大坪史弥・坂本正敬
編集協力:明石博之
[参考]The KeepCup Story: How They Became the World’s #1 Reusable Cup
https://www.upcyclestudio.com.au/blogs/sustainable-living/the-keepcup-story-how-they-became-the-world-s-1-reusable-cup
KeepCup founder on revolutionising coffee culture
https://www.ft.com/content/3df1d006-de86-11e8-9f04-38d397e6661c
'He said it was the stupidest idea he had ever seen'
https://www.bbc.com/news/business-52366981
'Stupidest idea ever': KeepCup founder Abigail Forsyth on how the reusable cup nearly didn't happen
https://www.abc.net.au/news/2017-05-18/abigail-forsyth-how-the-keepcup-nearly-did-not-happen/8537150
マイボトル運動を実施しています! ー 福井県
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/reduce/mybottleundo.html
1からわかる!プラスチックごみ問題(1) ー NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji17/
平成 28 年度沿岸海域における漂流・海底ごみ実態把握調査業務報告書 ー 三洋テクノマリン株式会社
http://www.env.go.jp/water/marine_litter/report_h28/enganmain1.pdf
漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査 福井県地域検討会報告書(案) ー 環境省
https://www.env.go.jp/water/marine_litter/model/kentou/region/fukui06/mat03_3.pdf
缶コーヒーのコク感アップと、おいしさを維持する実用技術を開発
https://www.kirin.co.jp/company/rd/result/report/report_019.html
使い捨てコーヒーカップよ、さようなら! 世界で広がるリユース&リサイクルの新しいかたち
http://www.thinktheearth.net/jp/sp/thinkdaily/news/living/1292coffeecup.html






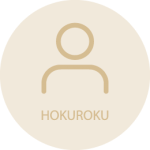


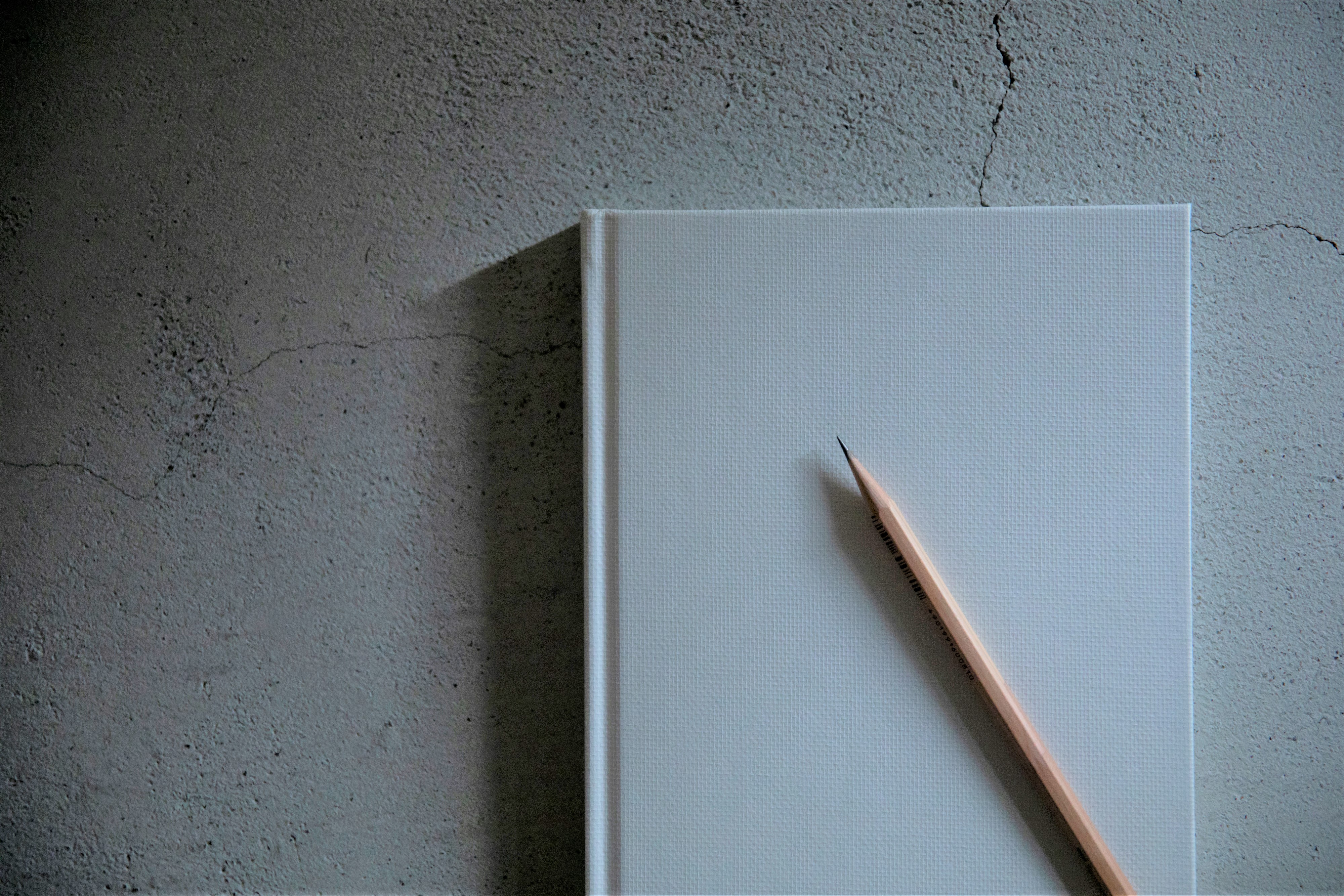




オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。