北陸の日本酒と料理のマリアージュ|酒匠と利き酒師によるレシピ考案編

vol. 04
細部に神は宿る
下木:酒器選びのためにまず聞きたいのですが、ミニバーセットの玄はお客さまの部屋の冷蔵庫に入れておきますか?
池森:部屋に置いておけるので常温がいいです。
下木:お部屋に用意しておく酒器は自由に選んでもいいという話ですよね。
池森:3部屋ありますので、その部屋分の数がある限り大丈夫です。
下木:酒器を全部見せてもらえますか?
池森:恥ずかしいな。
下木:すみません。
―― そう言えば下木さんは山中漆器の酒器の監修などもしていますよね。
せっかくなので酒器の基本的な考え方を教えてもらえないでしょうか?
酒器がどのような形になると、例えばどのように味わいが変化するのかなど。
下木:分かりました。日本酒の味わいは主にうま味と酸味でできています。
―― はい。うま味を基本に設計してきた日本酒が酸味にシフトしてきた話を先ほどしてもらいました。
下木:そのうま味と酸味のバランスは器を変えると変化します。
―― 具体的にはどのように変わるのでしょうか?
下木:基本的に酒器は下の部分と上の部分の2つの要素でできています。
形の異なるぐい飲み
例えば、この2つの酒器を見てください。向かって左は高台から腰・胴・口縁(口の触れる部分)に至るまで寸胴のようにストレートの形をしています。
向かって右は、高台から腰の部分でカーブを描いています。この角度で、酸味が強くなったり柔らかくなったりします。
左の酒器のように角ばっていると酸味は強くなり、右のように腰が丸くなっていると酸味が穏やかになります。
内面を触ってみると分かりますが、左はかくんとしていて右は丸いですよね。
(坂本、実際に触ってみる。)
―― 本当ですね。
下木:このカーブの有無が酸味のマイルドさに影響しています。
―― 高さとか深さは関係ないのですか?
下木:そうですね。日本酒の場合はそこまで関係ないです。高さとか深さは香りに影響を与えるのですが、日本酒は鼻で楽しむ香りよりも口に含んだ時の香り(含み香)の方が強いので。
―― 器の厚みはどうでしょうか?
下木:厚みもそこまで気にしなくていいです。
ただ、先ほどから言っている器の形状とは、器の外側ではなく内側の話をしています。
器が薄いほど外側と内側の形の見た目が少なくなり、器選びに失敗しにくくなるメリットはあるかもしれません。
また、口元の触れる部分の心地良さが、一般に市販されている厚い器だと乱雑になりがちです。
―― 口元の触れる部分の心地良さとは何でしょうか?
下木:口に触れる部分にいい感じの「r」があれば器は唇にフィットします。土のもの、例えば陶器とか磁器で厚みがあったとしても「r」があれば問題ありません。
―― 「r」とはアルファベットのアールですね。どういう状態でしょうか?
下木:例えば能作の酒器を横から見た時に、さすが能作さんだなと思うのですが口縁が「ピッ」としている。
―― ピッとしている?
下木:器の口縁が外側にちょっとだけ「ピッ」と反っている様子が分かりますか?
―― まあ、言われてみれば反っているような反ってないような。
下木:この反っている部分が舌触りを大きく変えるのです。
―― 下木さんのお店にある器は例外なくピッとしているのですか?
下木:ピッとしています。どんな仕事も神は細部に宿るというか、こうした細部にこだわった器はおのずと値段が高くなってしまう傾向にありますが。
下木さんのお店の酒器。撮影:坂本正敬
―― 酸味の話がありましたが、うま味についてはどうでしょうか?
下木:うま味に関しては酒器を横から見た時の腰の膨らみに注目してください。腰の部分に膨らみがあるとうま味が広がります。
いわゆる醇酒や熟酒など、味わいが濃厚な日本酒には腰の膨らんだ酒器が適しています。
―― 要するに、花のつぼみのような形の酒器を選べばいいのですね。
腰の部分が広い酒器
口縁が広がった酒器が薫酒には好ましい
―― 口に含んだ時の日本酒の香りという言葉が先ほど少し出てきました。酒器と香りの関係はどうでしょうか?
下木:口縁の広がりによって香りは変化が出ます。
大吟醸など薫酒の場合は香りを楽しみたいので口縁が広がったタイプの酒器が好ましいです。
口縁が広がっている酒器は含み香が広がり、口縁が狭まっているタイプの酒器は含み香の広がりが抑えられます。
口縁がラッパのように広がった酒器
―― 口に含んだ時の香りを「含み香」と呼ぶのですね。
ラッパのように酒器が広がっていれば香りが広がるとのイメージは想像がしやすいです。他に酒器で補足はありますか?
下木:熟成した日本酒、特に貴醸酒など酒を酒で仕込んで品質を安定させる位が高い日本酒は高貴なので、高台の高い器がいいかなと思います。
―― 高台とは、器の底に付けられた土台の部分ですね。
酒器ではないが、手前のガラスの器は口縁が「外にピッと出ている」と下木さんが絶賛した。第5話に再登場する。位が高い貴醸酒など熟酒に合った器は右手奥に見える高台が高い器
では、以上の酒器論を踏まえて「玄×ゲンゲ」でペアリングする際の最適な酒器とはどれでしょうか?
下木:そうですねえ。
(下木さん、蔵ステイ池森にあるさまざまな器を物色し飲み比べてみる。)
この椿の絵が描いてある酒器がいいかもしれません。
香りを強調するために口縁が少し広がった酒器を下木さんは選択した
(下木さん、試飲してみる。)
ああ、やっぱりこれ、すごくいいですね。ちょっと池森さんもこれで玄を飲んで他の酒器と飲み比べてみませんか?
池森:分かりました。
ああ、確かに。
下木:いいですよね。
池森:でもうちは客室が3部屋あるのですが、この酒器、残念ながら3つないんですよ。
下木:ああ、そうか。じゃあ、この酒器に似たあの切り子の器は数がありますか?
池森:あります。それこそ友達に言えばいくらでも手に入ります。
(下木さん、切り子の酒器で試飲してみる。)
下木:うん、ああ、これですね。完璧です。
―― 最高の酒器が見付かりましたか?
下木:はい。辛口 玄とゲンゲを切り子の酒器で楽しむ形が、この漁師町の氷見で楽しむ最高のペアリングだと思います。
切り子の酒器と180mlの玄
―― どういう風にいいのでしょうか?
下木:富山の氷見は石川の橋立などと一緒で大皿文化の漁師町ではないでしょうか。夫婦げんかで男女がお互いを主張し合う、そんな土地柄だと思います。
池森:そのとおりです(笑)
下木:若鶴は、氷見ではなく砺波の日本酒ですが、蔵ステイ池森は氷見にあります。
その氷見で合わせる玄とゲンゲのペアリングを考えると、漁師町である氷見で盛んな獅子舞のように強弱があり、同時にさわやかな香りもあって、日本酒がゲンゲに負けない印象になるこの酒器が合います。
―― 先ほどから聞いていると、下木さんはペアリングを考える時に、お酒を楽しむ場所の気候風土や文化、暮らす人たちの人間性に至るまで、さまざまな背景に思いを巡らせながら組み合わせを模索しているように思えます。
土地を知るためのキーワードとして民謡や獅子舞の音楽という言葉が特に何度も出てきました。
下木:はい。僕自身が料理人とペアリングをやる時にも音楽が必要になります。
―― 音楽が必要とは抽象的な意味ではなく、本当に音楽が必要だとの意味ですか?
下木:はい。料理人と日本酒を出す人がイメージを共有するために2人でまず音楽を決めます。
音楽を決めてから日本酒を並べ、音楽に合わせながら料理と器を当てはめていく作業になります。
僕の中で酒はリズムです。料理は、メロディーだと思っています。リズムとメロディーを合わせるために今回も〈YouTube〉で氷見の民謡とか獅子舞の音楽を聞いてきました。
その時に聞いた音楽に合わせながら玄とゲンゲと切り子の酒器を当てはめていった感じです。
―― 私の興味ある世界で言えば村上春樹さんの文章論を聞いているみたいですね。
氷見の民謡や獅子舞の音楽を頭に流しながらペアリングを考えていたとは恐れ入りました。
(大坪副編集長のコメント:蔵ステイ池森の宿泊者に出すミニバーセットの組み合わせが決まりました。
富山県民のベースにある味・玄にスモークしたゲンゲを合わせ、そのペアリングを切り子の酒器で楽しむ部屋飲みセットです。
最終回では、蔵ステイ池森で出す通常メニューとして薫酒・醇酒・熟酒のペアリングの試食が残っています。池森さん・下木さんのやり取りを通じてペアリング&マリアージュ論を総仕上げしましょう。)













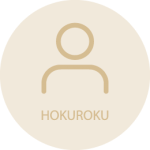







オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。