北陸の日本酒と料理のマリアージュ|酒匠と利き酒師によるレシピ考案編

vol. 01
「ペアリング」と「マリアージュ」の違い
池森典子さん。試食会当日の様子
「ペアリング」の教科書(前編)おさらい
前編「北陸の日本酒と料理のペアリング|若鶴酒造社長と利き酒師の対話編」は、富山県氷見市のまち中で日本酒バー併設の宿〈蔵ステイ池森〉を営む利き酒師の池森典子さんが、バーに訪れたゲストに宿泊まで楽しんでもらいたいと宿泊者限定のミニバーセット(日本酒と食べ物)を客室に置くアイデアを思い付いたところから始まります。
〈蔵ステイ池森〉の外観。撮影:柴佳安
その理由は氷見のまち中にもっと多くの人が泊まってほしいから。
まち中にある別のお店で食事を楽しんでもらう「泊食分離」のコンセプトで池森さんはまちの中心部に宿をつくりました。
しかし、オープンしてみると気さくなおかみの存在もあって、むしろ併設のバーが大盛況となります。
言い換えれば、当初の狙いである宿の利用者が少ない「逆転現象」が起きてしまったのですね。
氷見のまち中の様子
その話を聞いたHOKUROKUは、池森さんのミニバーセットづくりの過程を取材しながらペアリングの基本を教えてもらい、日本酒のペアリング論を浮き彫りにできないかと考えました。
蔵ステイ池森併設のバーコーナー。前編はここで取材が行われた。撮影:柴佳安
プラスして富山県にある若鶴酒造へ池森さんと一緒に出掛け、同社の社長や関連会社の専門家とも話をしてペアリング論に対する理解を深めます。
その場では、池森さんがつくるミニバーセットの食べ物の候補として、若鶴酒造が出すウイスキーブランドのつまみ〈HARRY CRANES〉とのペアリングアイデアも提案してもらいました。
〈HARRY CRANES〉の商品。撮影:柴佳安
前編で学びを深めたペアリング論と、若鶴酒造から出てきたHARRY CRANESのアイデアを基に、ミニバーセットの試作品を池森さんが後編ではつくります。
さらに、山中温泉で〈和酒 BAR 縁がわ〉を営む酒匠の下木雄介さんを蔵ステイ池森に招き、第三者の立場から試作品を味わってもらいました。
下木雄介さん。撮影:坂本正敬
酒匠とは、日本酒界のソムリエと言われる利き酒師のさらに上位資格で、極めて難易度の高い試験を突破した人のみが独占的に名乗れる日本酒の専門職です。
その酒匠を、石川県で初めて取得した人が下木さん。日本酒に関するNHKの番組にも登場するくらい北陸を代表する日本酒の専門家です。
せっかくの機会だからと池森さんが普段から併設のバーで出している食べ物と日本酒のペアリングも口にしてもらいます。
蔵ステイ池森併設のバーコーナーを試食会場にして、下木さんと池森さんの会話は大いに盛り上がり、日本酒のペアリング論がますます深まっていきました。
HOKUROKU編集長の坂本正敬が聞き手です。それでは後編を始めます。
合わなかった場合「合わない」と言います
―― いよいよ、この日が来ましたね。
池森:坂本さん。私が今どれだけ緊張しているか分からないですよね?
―― 大丈夫です。下木さんは優しい方ですから。
池森:どのような方なのですか?
―― そうですね。勝手に形容すれば「優しい森のクマ」といった感じでしょうか。困っている人が居たらハチミツを分け与えずにはいられないような。
池森:どんな方なんだろう。緊張で一睡もしていませんから。今日は。
(蔵ステイ池森の扉が開く。下木さん到着。)
―― ああ、下木さん。お久しぶりです。
下木:こんばんは。
―― もう、いきなり服装が準備万端じゃないですか。普段の仕事着で来てくださったのですね。
下木:ええ。今日は、試食会後にこちらで宿泊させてもらえるとの話ですから、とことん気合が入っています。
池森:いよいよ始まるのですね。どうしましょう。
―― 下木さん、ご紹介します。蔵ステイ池森の池森さんです。
池森:はるばるお越しくださり誠にありがとうございます。
下木:こちらこそ、お招きいただき、ありがとうございます。山中温泉で和酒BAR 縁がわをやっている下木と申します。
池森:よろしくお願いします。試食の準備を早速始めてもよろしいですか?
―― それでは池森さんがお酒を準備している間に私の方からあらためて今日の試食会の趣旨を説明させてください。まずは座りましょう。
(バーカウンターの席に腰掛ける。)
蔵ステイ池森の宿泊者限定の部屋飲み用のミニバーセットを池森さんが考え、その過程を記事化してHOKUROKUで特集を組みます。
利き酒師である池森さんが日本酒と食べ物の組み合わせを選び抜くプロセスをコンテンツ化できれば、日本酒と食事のペアリング論が浮き彫りになると思ったからです。
これまでの取材ですでに池森さんにはペアリング論の一般的な話を聞かせてもらっています。富山の若鶴酒造にも出向いて社長や関連会社の専門家ともペアリング論について話してきました。
部屋飲み用のミニバーセットをつくる当たって、池森さんは若鶴酒造のお酒をベースに、同社が出すウイスキーブランドのHARRY CRANESの中から食べ物を選ぼうと考えています。
これまでの流れを受けて今日は、池森さんの考える部屋飲み用のミニバーセットの試作を下木さんに実食してもらいたいわけです。
下木:分かりました。ただ一点だけ確認をさせてもらいたいです。
―― 何でしょうか?
下木:私の性格上、ペアリングが合わなかった場合「合わない」とはっきり言います。
お披露目コメントとして私が思ってもいない言葉をしゃべるような会にはしたくないです。
―― もちろん、そのために下木さんを呼んでいるわけです。
個人的に、別の媒体で取材させてもらった関係が下木さんとはあります。
お披露目コメントを出すだけの依頼を引き受ける方とは最初から考えていません。
下木:安心しました。
―― それでいいですよね? 池森さん。
池森:ぜひ。今日は、宿泊者用のミニバーセット案だけでなく普段からお店で出している料理もお出しします。こちらも意見をもらえればと思います。
下木:分かりました。
―― それでは私が、司会進行役を務める形で試食会&取材を始めさせてもらいます。
酸味を軸に日本酒を商品設計する酒蔵が増えています
取材の様子
―― 食べ物とお酒が出てくるまでちょっと基本的な質問をさせてください。
下木:はい。どうぞ。
―― 池森さんからは以前の取材で、日本酒の香味は縦軸と横軸を組み合わせた4つのジャンルに分類できるという話を聞きました。
ペアリング論の基本は、まず日本酒の香味の種類を知り、お酒の味や香りの特色に食べ物を合わせるだと学びました。
今日は、この4分類をベースにして試食会を進めさせてもらう形でよろしいですか?
下木:大丈夫です。ただ、このごろの日本酒業界では、海外でのマーケットを広げていく中で新しい味が模索されています。
もともと日本酒は、うま味を軸に商品設計をしていました。しかし、海外にマーケットを広げていく中で酸味を軸に商品設計する酒蔵が増えてきています。
欧米の人が慣れ親しんだワインの酸味に寄せて販路を広げていくというか。
その文脈で、日本酒自体が変わってきたのですから当然、食材との付き合い方も変わってきています。
ペアリングの問題を考える際にも、日本酒の香味と食材を合わせる、つまり「同調」させるだけではなく、ワインのマリアージュを学び、日本酒と食材の付き合い方を勉強しなければいけない時代になってきていると思います。
―― ペアリングとマリアージュとでは何が違うのですか?
下木:ペアリングの言葉には、あくまでも僕の表現ですが「同調」と「マリアージュ」の状態があると思います。
「同調」とは同じ成分を合わせてあげる。例えばみそのうま味と古酒のうま味を合わせて「おいしい」を倍加させてあげる。「ああ、おいしい」と静かに納得する感じ。
一方で「マリアージュ」はアッパー系なのです。料理にピッと少しすき間をつくってあげて、そのすき間に日本酒をスーッと入れて膨らませてあげる。
2つのつながった球が出来たら、それをぐいっとひねってあげるイメージです。
―― サンドウィッチマン風に言えば「ちょっと何を言っているか、よく分からないです」状態なのでもっと具体的にお願いします。
下木:「マリアージュ」で得られる感情を表現しろと言われたら「エレガント」と「エキサイティング」になるのかなと思います。
酒造組合のセミナーで去年金沢にフランスからソムリエが来ました。その時にソムリエが「エレガント」「エキサイティング」の言葉を何度も使っていました。
その話を聞きながら「エレガントってどういう状態?」と考えていたのですが、エレガントとはフランス音楽のイメージというか、ドビュッシーの〈月の光〉のように品があって洗練された状態をいうのではないかと思うようになりました。
一方のエキサイティングは食べて「楽しい、もっとほしい」という感じです。
この日本酒と食材の「マリアージュ」はもう近くまで来ていると思います。
例えば、僕が行ったニューヨークのマンハッタンにある日本酒メインのレストランでは、ちらちらっともうやっていました。
何年後になるかは別として、日本にも「同調」で終わらない「マリアージュ」のペアリングが来ると思っています。
―― 何か分かったようでまだ、すっきりしないです。どういったメニューが具体的に「マリアージュ」なのですか?
下木:例えば僕が、前に出したメニューで言えば新政酒造(秋田県)の生酒〈No.6〉と、6~7月くらいのプリっとした夏ガキでやりました。
食べた瞬間にジャージー牛乳のようなミルキーな味わいの広がる生ガキをちゅるんと口に含んであげてヨモギのお茶を飲み、酸味とパイン系の甘みがある新政を飲む。
―― ヨモギのお茶を飲むのですか?
下木:カキの磯臭さをヨモギのお茶が消してくれてくれるのです。
まず、カキのミルキーな感じがファーっと倍加すると同時にヨモギの香りが引き立ち、No.6のパインに近い甘酸っぱさが最後に包み込む状態です。
―― その結果、単なる「同調」のペアリングでは生まれない「ああ、もっと飲みたい」というアッパー系のエキサイティングな気持ちが生まれるのですね。
下木:はい。ワインの世界ではマリアージュは盛んなので、日本酒でも絶対に来ると僕は思っています。
―― ここまで池森さんと若鶴酒造に聞いてきた話は、ペアリングの中でも下木さんの言う「同調」の方だと思います。
池森さんは今日も「マリアージュ」ではなく「同調」の発想でペアリングを用意しているはずです。宿泊者限定のミニバーセットも「同調」の発想で設計する予定ですよね。
池森:はい。どうしましょう(笑)
下木:お部屋に置くミニバーセットなら「同調」でいいと思っています。
お客さまの気持ちを上げてしまうエンターテインメントの要素が「マリアージュ」は強いので、誰か注ぎ手が居ないとセーブができなくなる心配があります。
―― なるほど、では、今回は同調の方向で問題ないですね。いい文脈になってきました。池森さんの準備も終わったようですから試食会をスタートしましょう。
(坂本編集長コメント:世界に進出する日本酒の酸味が強くなっている話、言われてみると確かに思い当たる節があります。
トロントの取材でカナダを訪れた時にも現地のカナダ人のつくる日本酒を飲ませてもらう機会があり、ワインのような酸味に驚かされました。
なんだか伝統的で保守的にも見える日本酒の世界も積極的に変化を受け入れているのですね。
長い前置きは終わり。次からは試食会を通じて「マリアージュ」を含むペアリング論について考えを深めます。)












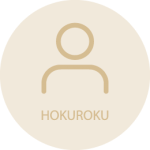







オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。