実録・金沢三茶屋街の遊び方|ひがし・にし・主計町の作法と体験記

vol. 05
金沢の生き字引
芸妓の小千代さん
お座敷遊びを体験し、お茶屋の世界について聞いてきました。この段階で時刻は20時30分。残り30分ほどでお開きです。
最後に、芸妓の唐子さんにはなぜ芸妓さんになったのか、常連のYさんとKさんにはなぜお茶屋に通うのかを聞いてみました。
―― それでは、芸妓さんの唐子さんにお聞きします。芸妓になるまでに大変な道のりがあるという話でした。なぜ、芸妓さんの道に進まれたのですか?
唐子:きっかけは芸妓さんへの憧れです。東洋史学を大学で専攻していて、伝統文化にずっと興味がありました。子どものころから笛も習っていました。
―― はい。
唐子:ただ、金沢で生まれ育ちながら茶屋街にはあまり行ったことがありませんでした。地元の方でも、茶屋街へ行った経験がないという方は意外に多いです。
―― 地元の方にとっても、若い人には特に、ちょっと遠い存在なのかもしれませんね。
唐子:大学生の当時は、茶屋街=古いまち並みが残っているという程度のイメージでお茶屋さんや芸妓さんの文化が今も残っているとは知りませんでした。
―― 今日、ここに来るまで私も全く同じ感覚でした。
唐子:そんな折、笛のけいこの帰りに茶屋街を通る機会がありました。歩く芸妓さんの後ろ姿をその時に初めて見かけたのです。本物の芸妓さんです。すごく格好いいなと思いました。
―― はい。
唐子:その後に新聞で、たまたま見かけた芸妓さんのインタビューで大学を出てからでも芸妓さんになれると知りました。
15歳くらいから修業に入らないと芸妓さんにはなれないと勝手に思っていたので「まだ間に合う」と知ったときはうれしかったです。
―― それで門をたたいたのですか?
唐子:はい。通っている笛の先生から紹介をいただいて芸妓の道を歩み始めました。
茶屋遊びの伝統をだんな衆には守り伝えてほしい
左からKさん、Yさん
―― では逆に、Yさん・Kさんにお聞きしたいのですが、どうしてお茶屋遊びを皆さんはするのでしょうか?
Y:お酒をただ飲むだけであれば他に行った方がもちろん安上りです。でも、お茶屋に通う価値は金銭的な問題だけではありません。
―― と言いますと?
Y:お茶屋に来ると、金沢の歴史や人間関係などさまざまな話を聞かせてもらえます。
K:そうだね。
Y:自分が、お茶屋に初めて来た時期は32歳のころです。それまでは中国で働いていて、金沢に帰ってきてから、大学の先輩に連れてきてもらいました。唐子さんの話ではないけれど、地元にいた時には、こんな世界があるとは全く知りませんでした。
―― お茶屋遊びは、ビジネスに役立つ・社交場の機能を果たしていると聞きますが本当ですか?
Y:金沢でビジネスをされている有名な方はだいたい、お茶屋さんに来た経験をお持ちです。お茶屋で人脈がつながるという話は今の時代も生きています。
―― 本当なのですね。
Y:「あの人は今、有名だけれど昔は、こんな苦労されていた」などと芸妓さんから聞かせてもらう話も面白いですし勉強になります。その価値は正直、プライスレスだと思います。
K:確かにね。
Y:ちょっと失礼な言い方かもしれませんが、小千代ねえさんなんて金沢の生き字引ですよ。
(一同、笑う)
―― 念のためフォローさせていただきますと「生き字引」は決して失礼な言葉ではありません(笑)
「失礼な言葉だ」と怒っている人をネット上のQ&Aサイトでも見た覚えがあるのですが「歩く辞書(ウォーキングディクショナリー)」と同じで、経験を積み、物事をよく知っている人を意味する誉め言葉です。
この「経験を積み」の部分に年月の経過を感じさせる部分があって、年月の経過=年齢を勝手に連想してしまう人が一部にいらっしゃるのかもしれません。
Y:だって、67年も続いている金沢青年会議所の初代理事長を知っているのですから。冷静に考えてすごい話ですよね。
Yさんが太鼓をたたく様子
ただ、情報収集や人脈づくりというビジネスの側面はお茶屋の魅力のほんの一部にすぎません。何より強調したい魅力は、芸妓さんたちの心配りや芸事の素晴らしさです。
K:心からほっとできたり伝統文化に直接触れられたりする場は他ではなかなか見当たらないかもしれませんね。
Y:そう。それに、これから金沢を、石川を、さらに言えば北陸を面白くしたいと考える若い方々にとっては、お茶屋遊びが1つの目標にもなると思うのです。お茶屋さんで遊べるくらいまで仕事を頑張ろうという意味で。
―― お茶屋に自由に通える状況は、すなわち経済的な成功を意味しています。
Y:ですから、北陸の若い方々こそお茶屋さんで遊べるくらいに仕事を頑張って、この空間を体験していただきたいと思っています。
K:私も同感です。お座敷で遊んでみて初めてビジネスが広がったり、心の余裕や大人のたしなみが学べたりすると実感できるはずです。
小千代:YさんやKさんのように金沢で会社を経営されている方々は、金沢の伝統文化の継承を重んじて笛・太鼓・長唄17を練習しておられます。そうした方々の集まりでは自分の芸事を披露するシーンも少なくありません。
ただ、芸事をたしなむ方も昔と比べて今は少しずつ減ってきておられる印象が残念ながら一方であります。芸妓だけでなく、金沢のだんな衆にはこれからも伝統を守り伝えていってほしいと願っております。
二次会・三次会の仕組み
二次会に向かう一行
ここで、その日の座敷はお開き。取材終了となりました。お開きになると場合によっては二次会・三次会の流れになるそう。
この日の取材後もYさんの「富山から来てもらっているのに1軒でお帰ししてしまっては失礼です」との粋なお誘いがあり、茶屋街のバーで二次会、片町のスナックで三次会が行われました。その間には唐子さんが着物姿で同行してくれます。
ただ、Kさんが耳打ちしてくれたように、芸妓さんを連れ回すとなるとその分だけ予算は膨らむのだとか。
どのようなシステムになっているのか、ちょっとハラハラしながらも失礼を承知で唐子さんに聞くと「○○時まで一緒にいた」と後に唐子さんからおかみさんに連絡が入り、その時間で額が決まるとの話です。
本当にお客と芸妓さん、おかみさんの信頼関係・信用で成り立っている世界なのですね。
ちなみに、初対面だったYさん・Kさんとは2時間の茶屋遊びを通じてすっかり意気投合していました。
お茶屋やお座敷遊びは得体の知れない存在で、ルール・料金・遊び方もそこまで世に知られていません。
「排他的」とか「内輪」といった言葉が頭に浮かび、私のような若造は、他の地域に住むよそ者という条件も加わって、一生かかわれない未知の世界だと思っていました。
ですが、今回の取材で外から来た「旅の人」でも遊べると分かりました。矛盾するようですが一方で「一見さん」お断りといった秘密性や排他性にこそお茶屋の魅力があるのかなとも感じます。
決して意地悪で他を寄せ付けないわけではありません。お茶屋に通うお客同士が安心して腹の中をさらし、末永く良い関係を生み出すためのシステムとも呼べるはずです。
その価値は、まだまだ他では代替できないと感じた一日でした。
(編集長のコメント:本当はここで「おしまい」のはずでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で社会の状況は取材後に一変しました。「コロナ」の波を茶屋街はどう乗り越えようとしているのか、日を改めて追加で取材しました。続きもぜひどうぞ。)







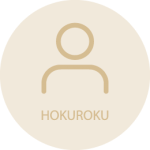







オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。