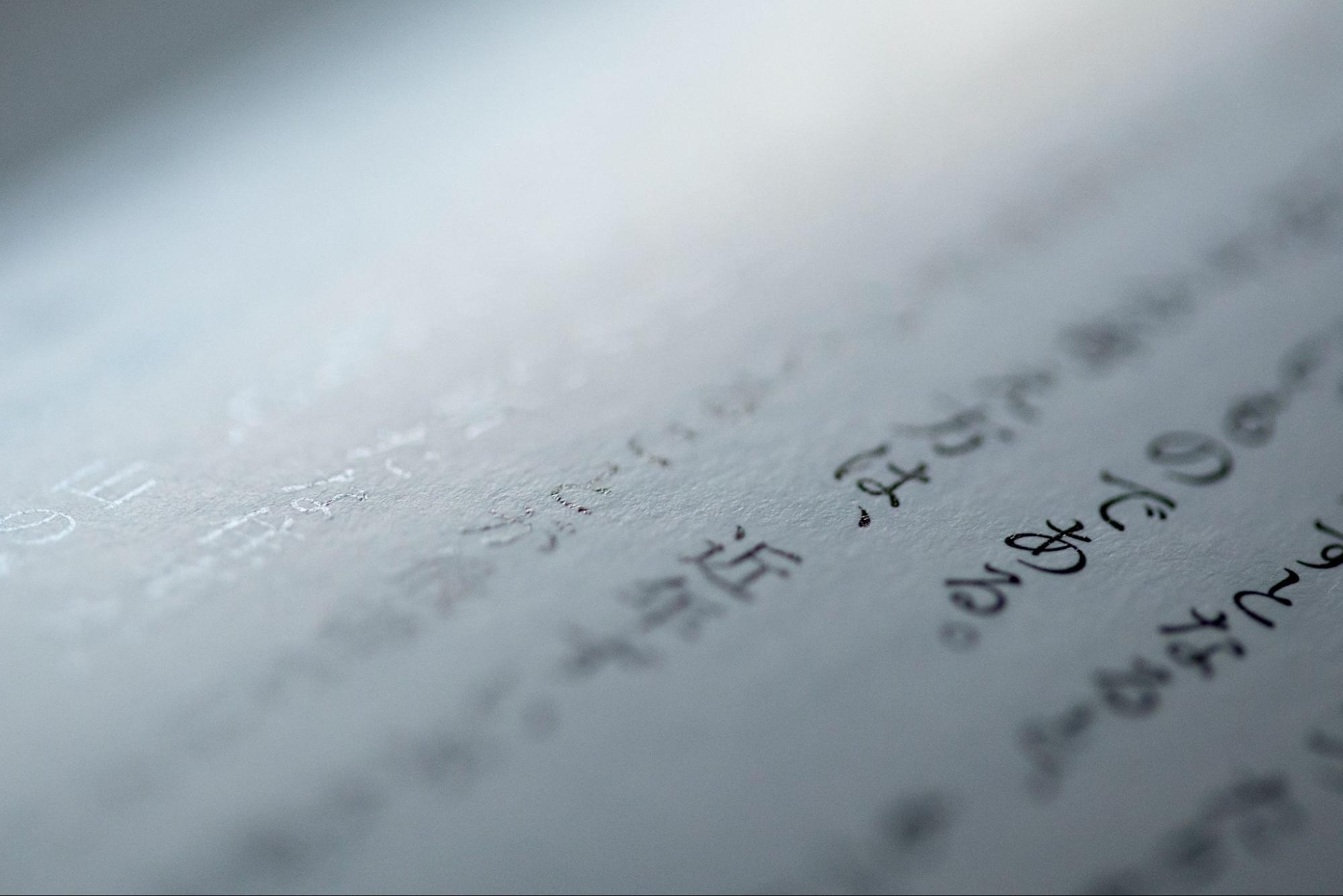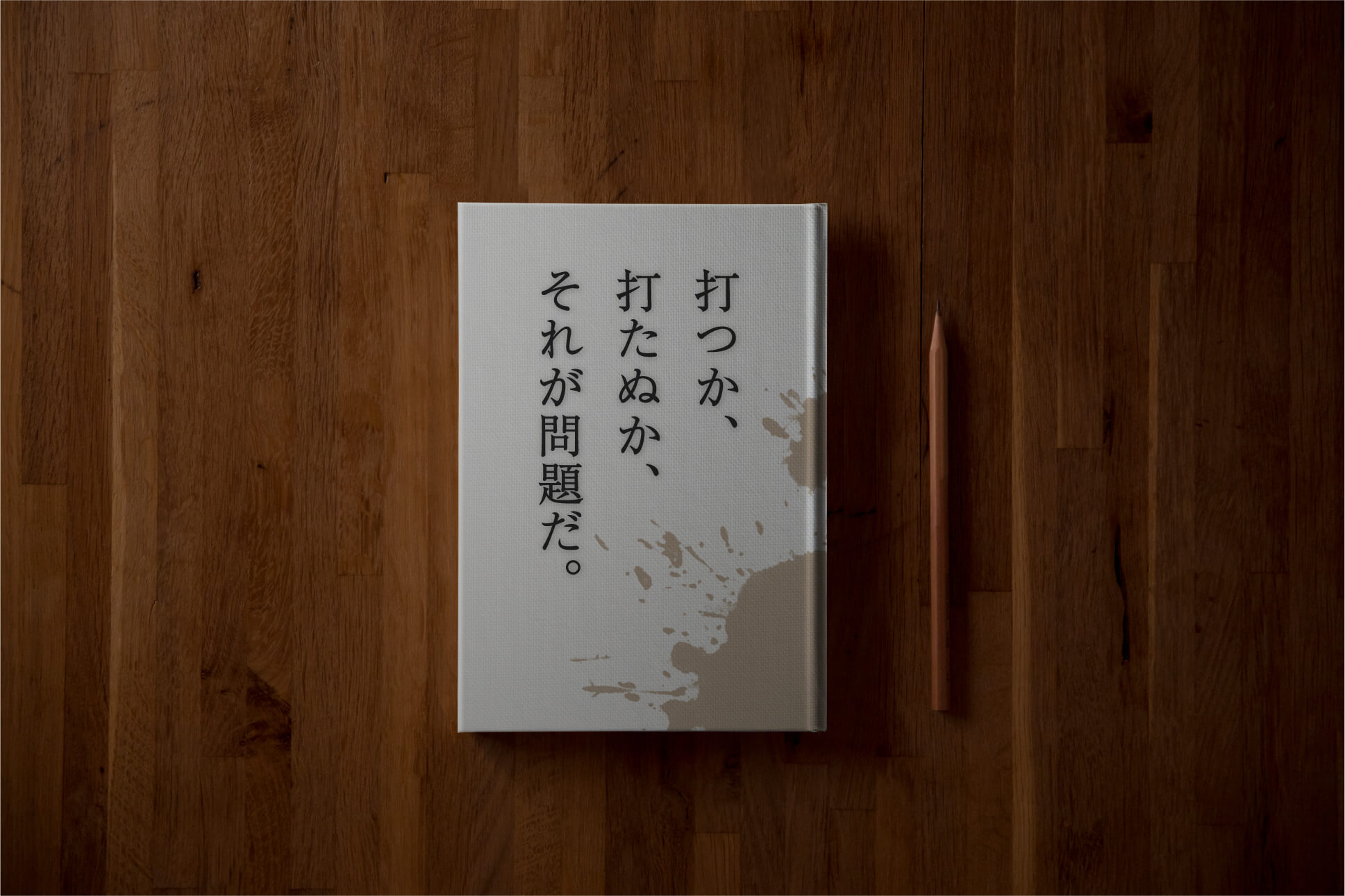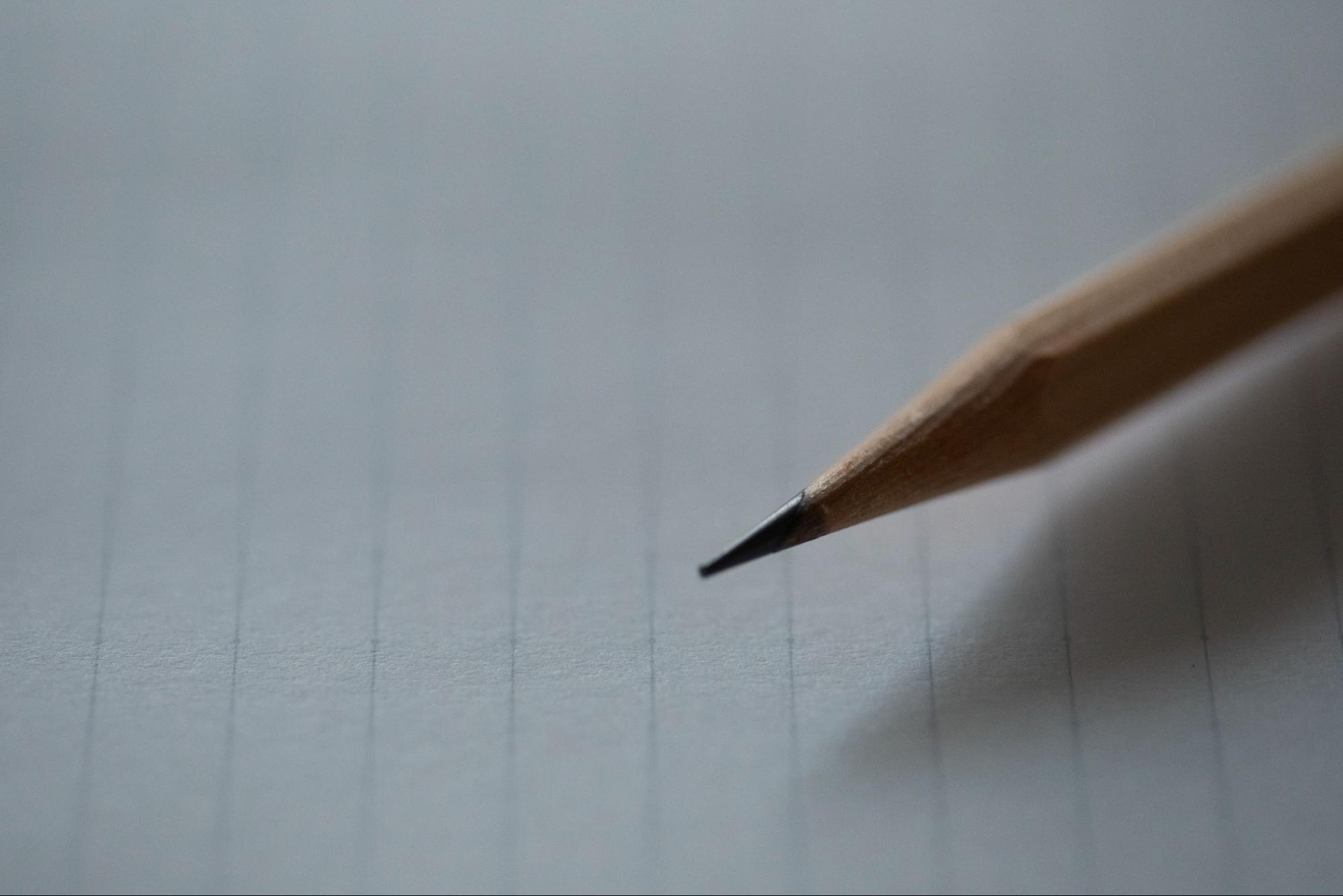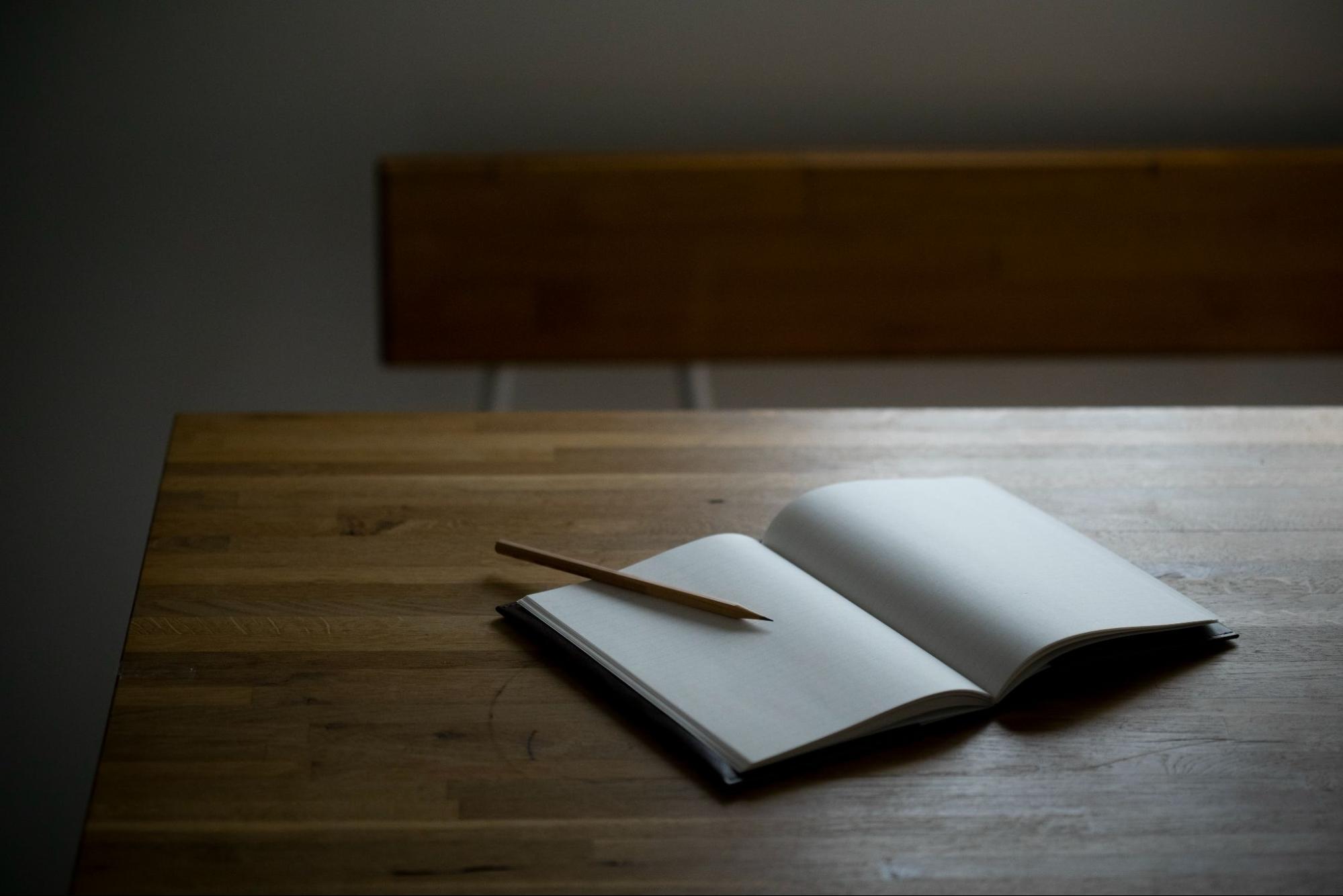正しく美しい「句読点」の使い方:学者と編集者で考える新・文章読本
情報発信のチャンスを誰もが手にする時代となりました。
記者、ライター、ブロガーなど言葉を扱う人たちはもちろん、伝達手段の発達とともに自分の言葉を伝える機会がさまざまな人に増えているはずです。
そこで、分かりやすくも美しい文章論を今回は考えます。中でも注目は読点(、)です。
句点(。)と違って読点(、)はなんとなく感覚で打っている人も多いのではないでしょうか。
現に、文豪・谷崎潤一郎ですら〈文章読本〉(中央公論社)で読点について「到底合理的には扱いきれない」と言っています。
もちろん、極言すれば、打ちたい場所に読点など打てばいいわけです。文字の読み書きが本当に苦手な人に対しては「正解などないから自由に打てば」と開き直った助言もできてしまいます。
しかし、無自覚に読点を使っていると文章がぶつ切りになったり、言葉と言葉の対応があいまいになったりと、分かりにくい文章になってしまいがち。結果として、教養のなさがにじみ出てしまう場合もあるはずです。
そこで「到底合理的には扱いきれない」読点の使い方に合理的で機能的なルールを定められないかとの思いから、富山大学准教授の宮城信さん、ならびに福井で人気の雑誌〈月刊fu〉およびポータルサイト〈ふーぽ〉の編集長を務める堀一心さんにオンラインで話を聞きました。
おこがましくも「新・文章読本」と銘打った特集。
恐らく、小学校の国語の授業よりも読点の使い方・打ち方が合理的に理解できるはず。最後までぜひ読んでみてくださいね。
HOKUROKU編集長・坂本正敬
目次
03
読書量の多い子どもは奇麗な読点を打てる(たぶん)
2021.07.02
こちらは月額会員向けのコンテンツです。
04
掛かる言葉を「背の順」に並べる
2021.07.03
こちらは月額会員向けのコンテンツです。
05
直してもらう喜び
2021.07.04
こちらは月額会員向けのコンテンツです。