何のために撮るのか
取材が行われた〈COMSYOKU〉のキッチンスペース。ガラスの向こう側はコワーキングスペース
―― はじめまして。〈HOKUROKU〉編集長の坂本正敬と申します。
今日は、編集部が置かれた、高岡のコワーキングスペース〈COMSYOKU〉までお越しいただき、ありがとうございました。
佐渡:こちらこそ、よろしくお願いします。
―― SNS(会員制交流サイト)時代の「物撮り(ぶつどり)」が本日のテーマです。そもそも「物撮り」とは、自分のお店の商品や料理などを広告・宣伝のために撮影する行為という理解で正しいですよね?
佐渡:はい。
―― SNSは今や、個人から大企業までが利用する大切な広告・宣伝ツールになりました。お店・商品の認知度アップに向けて写真投稿を日課にしている経営者・広報担当者は多いと考えられます。
ただ、投稿する写真のクオリティは情報の広まり方にすごく影響すると思います。現に、過去の取材でも専門家たちから同様の話を学びました。
なので今回は、広告写真を手掛ける金沢の写真スタジオのカメラマンズハウス1所属の佐渡亮介さんに、デジタル一眼レフの入門機を使って、さらには「スマホ」のカメラ機能を使って、情報発信に貢献してくれる写真撮影の方法を教えてもらおうという企画になります。
佐渡:了解しました。
―― この特集で想定する読者は基本的に、自分でお店を経営している人、もしくは、宣伝担当スタッフです。
もっと分かりやすく言えば、お店の宣伝にSNSを活用し、情報を拡散したりおブランディングを演出したりしたい人たち全員がターゲットです。
また「物撮り」を「物の撮影」とシンプルに考えた時、もっと広い読者も見えてくるはずです。
例えば、お出掛け先や食べたものを積極的に発信しているインフルエンサーの人たちや、たくさんの「いいね」をもらいたい普通のSNSユーザーたちも含まれるかもしれません。
それらの人たちが「映える」写真を投稿し続ければ、北陸のブランドイメージ向上にもつながり、移住者・旅行者が増えるという好循環まで結果として、見えてくるはずです。ちょっと大げさに言えば、ですが。
そこで今回は、取材の前半で、できるだけ簡単な言葉で「物撮り」の基本というか概論を教えていただきたいです。さらに、教えてもらったルールを基にして後半では実際に撮影にチャレンジしたいと考えております。
佐渡:分かりました。
佐渡亮介さん
―― ちなみに今回は、前半のインタビュー撮影と後半の撮影会を、HOKUROKUのウェブディレクターである武井靖に担当してもらいます。
武井:よろしくお願いします。
―― あえて今日は、インタビュアーに写真の専門家を手配しませんでした。
写真撮影のプロではない武井が教えを聞いてチャレンジしてみるという仕立てを大事にしたいと思います。なので、後半の撮影会には武井も参加させてください。
佐渡:いいですね。
―― さらに今日は、企画のテーマを聞き付けて、フォトグラファーとして富山で活動する笠原大貴さんも見学に訪れてくれました。
笠原:よろしくお願いします。
名刺交換する佐渡さん(中央)と笠原さん(右)
―― 後半の撮影会には笠原さんにも急きょ参加してもらって、笠原さんの「物撮り」論も教えてもらえればと思います。佐渡さん、構いませんか?
佐渡:もちろん構いません。
―― 後半は、プロ同士の技術が競い合うバチバチの撮影会になればと密かに思っています。お互い、けん制しまくりの。
佐渡:なんだかちょっと緊張してきました(笑)
―― インタビューをそれでは始めます。
専門家ではない人にシンプルに役立つ
―― 本題へ入る前にちょっといいですか。ちょっと失礼な言い方かもしれませんが佐渡さんは、ものすごく若い方ですよね。
広告写真を手掛ける金沢の名門写真スタジオから送り込まれる腕利きカメラマンだと聞いて「今日は大御所が来る」と気を張って待ち構えていました。
しかし、登場した人はさわやかな超若手の「イケメン」です。「元日本代表のサッカー選手・内田篤人さんが来たのでは?」と一瞬びっくりしてしまいました。
単刀直入で申し訳ないですが、お幾つなのですか?
佐渡:22歳です。
―― 22歳! ピチピチじゃないですか。
佐渡:まだまだ駆け出しです。今回の企画に僕が選ばれた理由はまず、スケジュールが取りやすい若手だったからだと思います。
また、スケジュール以外に会社の狙いがあるとすれば僕が、スタジオカメラマンとして一通りの基礎をたたき込まれたばかりの新人だからという理由もあるかもしれません。
―― 新人だからこそ基本に忠実なので今回のテーマに適していると。
佐渡:はい。おっしゃるとおり「物撮り」の基礎を学んだばかりで自己流のアレンジを変に加えていません。基礎に忠実な状態です。
だからこそ、写真の専門家ではない人たちへシンプルに役立つ情報が届けられると思います。
―― もうちょっと、佐渡さんについて詳しく聞かせてもらってもいいでしょうか。22歳と大変お若い方ですが、そもそも写真はいつ始めたのでしょうか?
佐渡:カメラマンズハウスに入った年齢は20歳の時です。諸事情で大学を中退せざるを得なくなり、仕事に就かなければいけなくなりました。
その時、カメラマンズハウスで人材を募集していると知り応募して拾ってもらった形になります。
―― それ以前にも写真は撮っていたのでしょうか?
佐渡:18歳ごろから写真は趣味で撮っていました。何か仕事をしなければと思った時、写真で生きていきたいと思って応募しました。
―― プロのカメラマンとしてこの若さでキャリアを歩み始めている背景には、そのようなストーリーがあったのですね。
「スマホ」でも十分にいい写真を撮影できる
そんな佐渡さんに、今回の企画をあらためて説明させてください。
先ほどもお伝えしたとおりカフェや雑貨屋、洋服店で情報発信をする人が想定する読者のメインです。さらに、インフルエンサーの人たち、SNSのユーザーたちも射程に入っています。
それらの読者を想定すると、デジタル一眼レフカメラの入門機を持っていたとしても、あくまでもオートモード設定で、買った時に一緒に付いてきた標準ズームレンズ2で撮っている状況が考えられます。
さらに言ってしまえば、デジタル一眼レフカメラすら持たずに、手持ちの「スマホ」で撮影する人の方が多いくらいの状況すら見えてきます。
このような企画の前提条件は佐渡さんから見て成立しそうに思えますか?
佐渡:全く問題ないと思います。それこそ、基本を押さえれば「スマホ」でも十分にいい写真を撮影できます。それ以上を求めたくなったらプロに頼めばいいだけの話です。
―― さらに言えば「物撮り」を「ものどり」と読んでしまうくらいの人たちに、撮影の基礎を分かりやすく伝えようとしているわけです。
一般的な写真の入門書に書かれているさまざまな専門用語があるじゃないですか。例えば、露出補正・ISO感度・ホワイトバランス・絞りなどマニュアル撮影に関する情報です。これらも全部思い切ってカットしたいと思っています。大丈夫でしょうか。
佐渡:問題ありません。
―― 安心しました。では、道具についてはどうでしょうか。
料理撮影の入門書などを読むと最低でも三脚が必要だとか、自作でもいいのでレフ板を用意しようだとか、撮影用の小物を用意しておこうだとか、道具に関する記述があります。
カメラ以外のそれらの道具もできれば全部なしでお願いしたいのですが構いませんか?
佐渡:カメラさえあれば大丈夫です。後は、お店の環境を利用して十分に撮影できます。
―― 繰り返しになりますが、カメラ以外は本当に何も必要ないのですか? 観葉植物だとかオーナメントを「物撮り」の背景に脇役として入れるみたいなテクニックを入門書では見るのですが。
佐渡:プロの「物撮り」には主役の奥に脇役が写っている写真が確かにあります。しかし、小物を使うなどのテクニックはあくまでも結果論です。
例えば、プロの「物撮り」を見て背景に何かが置かれているとします。そうなると「『物撮り』では背景に物を置くといい」とルールとして考えてしまうかもしれません。
しかし、背景に何かが置かれた理由はあくまでも、何かを置く必然性がその写真にあったからです。テーマと狙いがあり、その狙いを実現するために背景に物がたまたま必要だっただけです。
―― 興味深い話ですね。小物・脇役を置くが目的なのではなく、目的をかなえるプロセスで結果として小物が必要になったから置いただけだと。
佐渡:「物撮り」において大切なポイントは「何を・何のために撮るのか」です。「狙いとテーマを決めてそこからぶれない姿勢」とも言い換えられます。
―― テーマと狙いがあるからこそ、その狙いを実現するために演出が決まってくるのですね。いわゆる「手段を目的化しない」といった話とも近いのかもしれません。
編集部まとめ
何のために「物撮り」するのか最初に明確にする
佐渡:素人の方が投稿するSNS写真を見ていると、情報の多すぎる写真が目立つ気もします。テーマが決まっていない写真とも言い換えられるかもしれません。
素人の方こそ、テーマを決めたら情報を足すのではなく引くといいと思います。色も物も減らす「引き算」の考えで自分が撮りたい何かを際立たせた方が、いい写真を撮れる可能性も高くなると思います。
―― 必要に駆られて私自身が「物撮り」する時「背景に何かを入れよう」「ちょっとお皿の端を切ってみよう」みたいなテクニック先行の考え方になっています。
そうしたテクニックを根拠なく盛り込むのではなく、テーマをはっきりとさせたら、余分な要素はむしろ引いた方がいいのですね。
編集部まとめ
「物撮り」では徹底的に情報を引く
(副編集長のコメント:足し算ではなく引き算で「物撮り」を考える。プロの言葉には説得力がありますよね。
引き続き話は深まっていきます。それらの話を踏まえた後半の撮影会はすごく盛り上がりました。最後までぜひどうぞ。)








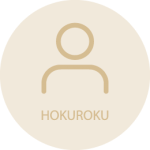
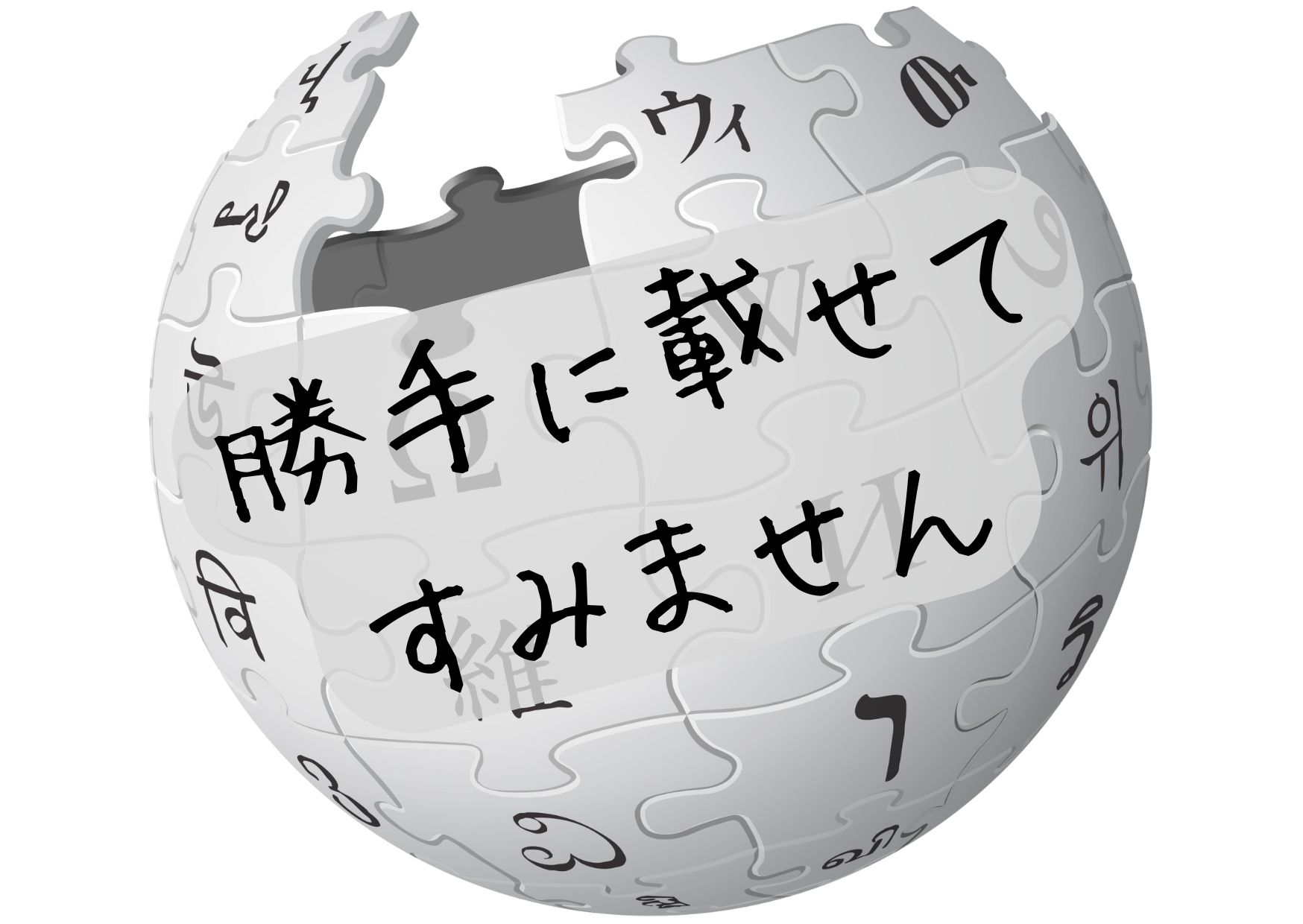



オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。