憲法学者も「許容できない」
現在の市庁舎前広場。写真は2016年(平成28年)の整備事業が終わった後の状態
法律家の序言
〈HOKUROKU〉運営メンバーにして弁護士の伊藤建です。
この連載「法律家の『謎解き』。弁護士Iからの挑戦状。」では北陸3県にまつわる裁判を取り上げ、論理と人情の交差点で悩んだ法律家の足跡を「謎解き」スタイルでたどります。
法律というと血も涙もない論理の世界だと思うかもしれません。しかし過去には論理と人情がせめぎ合いの末、人間味のある判決が出た、あるいは逆に憲法学者や法曹関係者が「到底許せない」と批判する判決が出た有名な裁判が少なくありません。
今回取り上げる北陸の事件は金沢市庁舎前にある大きな「広場」が舞台になります。市民団体と金沢市との間で「広場」を巡る考えが対立し、その争いは最終的に最高裁判所にまで持ち込まれました。
どのように裁判官は判決を下したのか、憲法学者や法曹関係者はその結論をどのように評価したのか。一緒に考えてみてください。
プロローグ
広坂の交差点。撮影:坂本正敬
金沢を代表する観光スポットといえば日本三名園の1つとして有名な兼六園だ。
兼六園から金沢城公園との間にあるお堀通りを下ると右手に美しい並木道が見えてくる。
この並木道は「広坂通り」とかつて呼ばれていた。百万石通りとして現在は親しまれており、金沢市を代表する繁華街・香林坊へと続いている。
〈金沢21世紀美術館〉撮影:坂本正敬
広坂の交差点の左手にはガラス張りの〈金沢21世紀美術館〉があり、少し進むと右手には格調高い建物が見えてくる。
この建物は1924年(大正13年)に建てられ、2002年(平成14年)までの78年間、石川県庁舎として使用されてきた。
〈石川県政記念 しいのき迎賓館〉写真:石川県観光連盟
現在は正面を残して現在は減築され、2010年(平成22年)に〈石川県政記念 しいのき迎賓館〉として生まれ変わっている。北陸の人たちであれば誰もが知るエリアに違いない。
さらに足を進めると視界が広がり、2つの大きなスペースが見えてくる。
市庁舎前広場。奥は市役所第一本庁舎。写真は現在の様子で2016年(平成28年)の整備事業が終わった後の状態である
1つ目は、市庁舎前広場と呼ばれる。香林坊に向かって左手に見える大きな「広場」(もともと庁舎へのアプローチ空間なのでかっこ書きの「広場」表記)で、オレンジ色の金沢市の市役所第一本庁舎が奥に見える。
〈四高記念文化交流館〉
赤レンガの建物はかつて旧制第四高等学校、通称「四高(しこう)」の校舎として使われていた。
現在は〈四高記念文化交流館〉に改装され、文学や資料が展示されている他、貸会議室は各種の研修会やコスプレイヤーの撮影会の控室などに使われている。
百万石通りからは見えにくいが「四高」の奥にある広場はかつて中央公園と呼ばれた。「四高」の改装に伴い「いしかわ四高記念公園」に改められた。
今回の「謎解き」は、これら2つの広大なスペースを巡る物語である。
広場としての役割が認められてきた
いしかわ四高記念公園
一般に広場にはどのような役割が与えられていると考えるだろうか?
誰もが自由に出入りできる上に市民の憩いの場として普通は思うだろう。何かのイベントや集会の開催地にも当然なる。
市庁舎前広場も一緒で、これまでに〈かなざわ国際交流まつり〉などのイベント、集団的自衛権行使容認や軍国化に反対する市民集会、金沢市長選挙の出陣式などさまざまな用途に使われてきた。
金沢市長自身も、市役所第一本庁舎へのアプローチ空間をメインとしつつも憩いの空間やイベント空間として機能充実を図る方向性を示していた。
後に裁判となった際の判決文によれば、
“平成24年度に本件広場の活用方策を検討する本件広場活用計画策定事業費として205万4000円を支出している”
“同事業においては本件広場につき「庁舎へのアプローチ空間」をメインとしつつ,「憩いの空間」や「イベント空間」としての機能の充実も図るという基本的な方向性が示されており”
という事実もある。
市役所第一本庁舎前は庁舎の敷地の一部扱いにとどまらず、一般的な意味における広場の役割が金沢市によって認められてきたのだ。
北陸の人であれば分かると思う。市庁舎前広場の周囲には壁があるわけでもない。生垣で周囲と仕切られているわけでもない。道路に面して完全に開かれており、庁舎前の空間を市民は自由に行き来している。
写真左から百万石通り、歩道、右手奥が現在の市庁舎前広場。写真は2016年(平成28年)の整備事業が終わった状態。裁判で「広場」が問題となった時期は改修前の2014年(平成26年)である。とはいえ改修前後でそれほど大きな変化はない
同じ市庁舎でも例えば富山市庁舎・福井市の市役所庁舎のアプローチ空間とは設計上の思想が違うようにも思える。
富山市庁舎。三角屋根の下にアプローチ空間があるが生垣で囲われている。写真:富山市観光協会
ところが2014年(平成26年)、市庁舎前広場を使ったある市民集会の開催について利用が不可と判断された。
「イベント空間」として機能充実を図る方向性を示していた金沢市によって市民集会の開催が不許可とされたのだ。
この決定が後に憲法学者をして「許容できない」と言わしめた裁判の引き金となる。
市中パレードの中止を求める集会
百万石通り
事の発端は2014年(平成26)5月24日にさかのぼる。石川県政記念 しいのき迎賓館からお堀通りに向かって、金沢駐屯地の基幹部隊・第14普通科連隊1の創隊60周年を記念した市中パレードが予定された。
2014年と言えばIS(イスラム国)が中東で勢力を拡大し、長野県で御嶽山が噴火して、広島県で大規模な土砂災害があった年だ。STAP細胞の騒ぎもあった。
市中パレードが行われると知った金沢市民Xらは同年5月19日に、市庁舎前広場で市中パレード中止を求める集会を開こうと計画した。
陸海空三自衛隊による市中パレードを金沢市民Xらは「軍事」パレードと考えたからだ。
集会に先立つ5月2日、市庁舎前広場を管理する金沢市長に書面を通じてXらは許可を求めている。市庁舎前広場を使うために必要な正式な申請方法である。
しかし12日後の5月14日、市中パレード中止を求める集会開催の申請は金沢市によって不許可とされた。
不許可とした金沢市側からは「市の定めたルールで、物事に対する『賛成』や『反対』を訴える集会、いわば、政治的な行為に市庁舎前広場は使えない」と説明がされた。
繰り返しになるが過去に金沢市長自身が市庁舎前広場の利用について、憩いの空間やイベント空間として機能充実を図る方向性を示してきた。
さらに言えば、市民集会・金沢市長選挙の出陣式など、物事に対する賛成や反対を問う集会も行われてきた。
にもかかわらず、自衛隊の市中パレード中止を訴える集会の利用は金沢市から不許可と判断されたのだ。
この判断を巡り今回の不許可処分は違法であると、金沢市民Xらは金沢市を相手取って金沢地方裁判所に提訴した。
金沢市民Xらと金沢市による法廷闘争の始まりである。
(坂本編集長のコメント:金沢市民のみならず北陸の人であれば市庁舎前広場がどのような場所か想像が付くと思います。
金沢21世紀美術館の敷地の隣、市役所地下駐車場に出入りもできる大きなスペースですね。
あの「広場」を巡って過去に法曹関係者や憲法学者を騒がせる事件が起きていたとは知りませんでした。
引き続き第2回の「事の経緯」へと読み進めてみてください。)












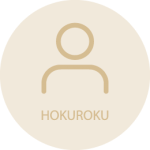






オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。