実録・金沢三茶屋街の遊び方|ひがし・にし・主計町の作法と体験記

vol. 01
金沢市民すら茶屋街を知らない
ひがし茶屋街の様子。撮影:大木賢
ちょっと前書き
目次ページに引き続き〈HOKUROKU〉編集長の坂本です。副編集長の大坪にバトンタッチする前に口上の一幕を前書きとして書かせてください。
北陸を代表する観光地の茶屋街が金沢にはあります。この茶屋街とはそもそも何なのでしょう。
詳しく後で1紹介しますが、金沢のひがし茶屋街2にあるお茶屋〈中むら3〉で活躍する芸妓4(げいぎ・げいこ)の唐子(とうこ)さんいわく、金沢生まれ・金沢育ちの唐子さんですら「茶屋街は、古いまち並みが残る場所」程度の理解しか大学生のころまでなかったそう。
今回の取材にあたって〈藤乃弥5〉というお茶屋を紹介してくれた金沢の経済人であるYさんも同じです。
Yさんは、金沢生まれ・金沢育ちでありながら、先輩に連れてきてもらうまで、茶屋がどんな世界なのか全く知らなかったと言います。
生粋の金沢市民すら、よく分からない・知らないのです。富山、および福井の人であればなおさらですよね。
3つの茶屋街が金沢には存在する
浅野川大橋から眺めた主計(かずえ)町茶屋街。撮影:坂本正敬
最初の問題にあらためて戻ります。茶屋街とは何なのでしょう。
金沢の茶屋街の誕生は江戸時代にさかのぼります。城下に点在していた茶屋が藩公認の下でまとめられたり6、風紀の乱れで廃止7されたり、再び許可8されたり。ざっくりと言えば紆余(うよ)曲折がありました。
明治・大正・昭和に入っても浮き沈みが続きます。明治の後半から大正にかけては盛り上がりを見せ、第一次世界大戦の好景気でもうるおいましたが、第二次世界大戦を境に時代が大きく変わると、茶屋や芸妓の数は劇的に減っていきます。
その流れは全国でも一緒です。茶屋街は、金沢以外だと、花街(かがい)、芸者町(げいしゃまち)、花柳界(かりゅうかい)などと呼ばれます。芸妓さんたちが活動するエリアという意味では全て同じ言葉。
京都(五花街)・東京(六花街)を筆頭に全国各地に花街はあります。しかし実態は、どこも規模を縮小し、消滅した花街も残念ながら中にはあります。
にし茶屋街。撮影:坂本正敬
その変化の波はもちろん金沢にも及んでいます。それでも金沢には、ひがし・にし・主計(かずえ)町という3つの茶屋街が今でも存在しています。
数こそ減っていますが現役の芸妓さんも数十名の規模で活躍しています。それほど大きいとは言えない地方都市の金沢でどうして茶屋街が生き残れているのでしょうか。
今回の特集では、その理由を確かめる目的も兼ねて茶屋を実際にのぞかせてもらいました。
金沢の経済人として茶屋遊びの文化を守りたい
ひがし茶屋街の周辺。撮影:坂本正敬
取材は、2019年(令和元年)の末に行われました。新型コロナウイルス感染症の影響が出てくる前です。
当日は雨でした。金沢の茶屋街は「一見さん」お断りの世界。この取材の取り付けも一筋縄ではいきませんでした。
「一見さん」の壁を越えさせてくれる紹介者を探す必要がまずありました。さまざまなつてをたどる中で意外にも、最も身近な編集部の中に、茶屋通いする金沢の若手経営者を知る者がいました。連絡を入れると協力してくれるとの話。
この若手経営者とは冒頭のYさんです。Yさんは金沢の経済人として「お茶屋の文化を守りたい」という思いがあり、紹介の協力を快諾してくれました。
Yさんが友人と茶屋へ行く、業界の言葉で言えば「お座敷を打つ」(宴会を開く)際にHOKUROKUも同行させてもらい、現場の様子を取材するという計画を立てます。
しかし今度は、大変な迷惑をYさんに掛ける形になりました。Yさんを通じてでも取材者の帯同を認めてくれる茶屋は容易に見つかりません。
内部の様子をあけすけに何でも明るみにする行為が必ずしも粋だとは限らないからだと思います。
それでも、粘り強いYさんのお願いにより、ひがし茶屋街にあるお茶屋〈藤乃弥〉のおかみ吉川弥栄子さんが、われわれのお座敷への同行を寛大にも受け入れてくれました。
吉川弥栄子さんは、お茶屋のおかみを務めながら、同じひがし茶屋街で〈照葉(てりは)9〉というワインバーも経営しています。
昨年末、この藤乃弥で取材は行われました。茶屋とはどのような場所で、どのようなルールがあり、芸妓さんの芸事にはどのような魅力があるのか、浅学ながら伝えられればと思います。
次の回からは、茶屋遊びを実際に体験した副編集長にバトンタッチします(取材現場にはもちろん私も行きました)。最後まで楽しんでくださいね。
(副編集長のコメント:第2回以降は、HOKUROKU副編集長の私大坪が行くお茶屋遊びの世界です。ああ、緊張した―。)
23つの茶屋街が金沢にはある。ひがし茶屋街はその中の1つ。
3ひがし茶屋街に5つある茶屋の1つ。石川県金沢市東山1-14ー7
4歌、三味線、舞踊などを酒宴の場で披露しお客を楽しませる芸者。
5ひがし茶屋街に5つある茶屋の1つ。石川県金沢市東山1-14ー12
61820年(文政3年)
71831年(天保2年)
81867年(慶応3年)
9石川県金沢市東山1-24ー7





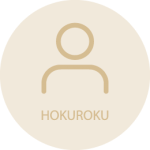







オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。