読者や視聴者と二人三脚で
〈HOKUROKU〉の取材の様子。写真:山本哲朗(※写真はイメージです)
〈HOKUROKU〉は、インターネット上で運営されるウェブメディアです。
先だって福井に暮らす60代の女性に「ウェブメディアって何?」と聞かれたので、
「インターネットの双方向性を最大限に活用しながら、知識と情報の体系化を、リーダーシップを発揮して先導していくサービスです」
と、答えました。しかし、自分でしゃべりながら「なんて下手くそな説明なのだ」と思いました。
あらためて考えてみると、ウェブメディアとは何なのでしょう?
まず、ウェブメディアというより、ウェブメディアを成り立たせているインターネットと従来のマスメディアの関係から考えると分かりやすいかもしれません。
米ニューヨーク市立大学大学院ジャーナリズム学科教授のJeff Jarvisさんによれば、インターネットは、従来のマスメディアが謳歌(おうか)していた「希少性の独占」を破壊したといいます。
もともと、新聞や雑誌の紙面、あるいは、ラジオやテレビの放送時間は限られていました。その限られた(希少性の高い)紙面や放送時間を使い、大勢の人(マス)に情報を届ける立場を独占してきたわけです。
その立場が独占的であったからこそ、メディアの提供する広告枠の値段も、極端な言い方をすれば「言い値」のような状況が許されてきました。
しかし、インターネットの登場により、情報伝達のための「紙面」と「放送時間」がほぼ無限になって、マスメディアは独占的な立場を徐々に失い始めています。
情報の発信者に誰もがなれる時代の始まりです。情報を受け取る側も、マスメディアが取捨選択した情報ではなく、自分の好みの情報を直接取りにいくようになりました。
こうなると、国民の大勢が、同じ情報を同じ時間に同じマスメディアを通じて受け取るという垂直方向の関係は崩れます。
ウェブメディアは、このマスメディアの希少性の独占を破壊し、「マス」をも殺したインターネット技術の上に成立するメディアです。
当然ですが、その最前線では、垂直方向ではなく水平関係で、読者や視聴者と協調しながら二人三脚で歩んでいく、インターネット時代のメディアのあり方が模索されています。
この徹底的な読者との双方向性と協調関係は、ウェブメディアの特徴であり可能性だとHOKUROKU編集長の私(坂本)も考えます。
こんな話を、冒頭の60代の女性に問われた時、答えたかったわけです。しかし、この説明でもちょっと難しい気がします。もっとシンプルに、説明する言葉を覚えなければいけません。
読者とのやり取りがウェブメディアの生命線
HOKUROKUにとって、読者との関係を深める大切な場所の1つが、特集や連載の各記事に用意されたコメント欄です。
何かのテーマを特集で取り上げ、意見を主張し、その投げ掛けに読者が応じて議論が始まる、ウェブメディアのコンテンツがそうしたやり取りで完成すると考えればコメント欄はすごく大切なはず。
どころか、読者とのやり取りの有無が、ウェブメディアの生命線だったりするわけです。
しかし、冒頭から述べているように、コメント投稿は今のところ1件だけです。
こうなってくると、HOKUROKUの特集が、コメントするに足りないという可能性も出てきます。
もちろん、この方面の努力と創意工夫は真剣に、さぼらず続けていかなければいけない話ですが、もしかすると他方で、コメント機能があると読者に知られていない可能性も考えられるわけです。
そこで「HOKUROKUにも〈Yahoo!ニュース〉のようにコメント欄があるんだよ」と全力でアピールしたいと思いました。
(副編集長のコメント:長い前置きになりました。次回はなぜ、HOKUROKUのコメント欄を「オプエド」と呼ぶのか編集長が語ります。)



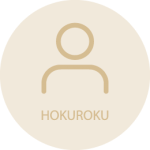






オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。