東シナ海で吹いた先触れ
巡洋艦・矢矧。Licensed under public domain via Wikimedia Commons
パンデミック警戒フェーズ1:1~3
シンガポールの港に停泊する日本の巡洋艦2・矢矧(やはぎ)から突如として4名の熱性患者が出た。日付は1917年(大正6年)11月24日、第一次世界大戦3の終わるおよそ1年前である。
北陸から5,000km近く離れたシンガポールはマレー半島南端に位置する交通・軍事上の要地だ。
イギリスとの同盟関係から日本は太平洋とインド洋における輸送船護衛を引き受けており、巡洋艦・矢矧はその任務の一環で11月9日から停泊していた。
「普通ノ風邪ナルベシ」
シンガポール港(1890年(明治23年))。※写真はイメージです。Licensed under public domain via Wikimedia Commons
4名の熱性患者が出た巡洋艦・矢矧(やはぎ)の軍医官は、にわかに発生した患者を「普通ノ風邪ナルベシ」と上官に意見した。
どれだけの忖度(そんたく)がこの発言に含まれていたか今となっては分からない。しかしこの意見が1つの根拠となり、巡洋艦・矢矧は数日後4にシンガポールを離れマニラへ向かった。この決断が後に命取りとなる。
巡洋艦・矢矧はシンガポールに入港する前から悪病の世界的な流行について情報をつかんでいた。
日本の他の軍艦5でも熱性患者は出ており、寄港地のシンガポールでも病勢が確認されていた。
現に巡洋艦・矢矧はシンガポール港に入って6からしばらく7海兵に上陸を許していない。公用で仕方なく上陸しなければいけない人員には予防薬まで渡している。
しかし、当時の将校は、下士卒(海兵)の士気を気にしたと考えられる。「陸上の病勢もほとんど終息し、ますます好況に僚艦も上陸を許可し、何ら異常ない」として、最初の熱性患者が出る2~3日前8、海兵を半分ずつ4時間に限り上陸を許していた。
冒頭の4名の熱性患者がこの後で確認された。軍医官は兵員室に患者を隔離して手当てする。その努力もむなしく新たな患者が見つかった。間もなく9、体調不良の下士卒は10名に達している。
それでも軍医官は「普通ノ風邪ナルベシ」と考えた。患者の経過も良好で10名の中には甲板で寝た者も含まれていた。「甲板で寝たのだから風邪でも引いたのだろう」と判断されたのだ。
巡洋艦・矢矧はシンガポールで最初の患者4名が出てから1週間ほど10してマニラに向かった。この南シナ海の航行中に艦内で集団感染が発生した。現代流に言えばクラスターの発生である。
軍医長、倒れる
南シナ海。※写真はイメージです。Sunset in the South China Sea by bvi4092
シンガポールを出港したその日、巡洋艦・矢矧(やはぎ)は間もなく海上で日没を迎えている。夕食後に軍医官が検診を行うと、20名以上の熱性患者が新たに見つかった。
翌日11には、1日かけて数回の検診が行われている。10数名の患者がその都度見つかり、午後の段階で艦内の患者は69名にまで増えた。出港から、わずか2日目の出来事である。
この段階でもちろん、シンガポールに引き返す選択肢も矢矧にはあった。シンガポールからマニラへの航海は、およそ6日間が予定されている。出港からそれほど時間もたっていない。引き返すには絶好のタイミングだ。しかし、一度動き始めたオペレーションは往々にして中止が難しい。マニラへと向かう道を矢矧は選んだ。
決断の根拠は3つある。1つ目として、シンガポールで流行している悪病は他の地域の流行病と比べて深刻な病状に陥らないという調査報告があった。2つ目には、乗組員も新陳代謝を高めつつ感染の予防に務めれば問題ないという意見もあった。
さらに、3つ目として、目的地のマニラの方が「陸上病院、および医薬等に余裕がある」という憶測に近い情報もあった。余裕があると「信じられる」と報告書には書かれている。
しかし、この段階ですでに艦内では集団感染が発生している。出港から3日目12の午前には新たに50名近くの患者が見つかり、その日の午後には看護師の1名が病に侵された。
さらに、4日目13には別の看護師も倒れ、5日目14には、わずかな将校と30~40名の海兵を除いてほぼ全ての乗組員が感染した。巡洋艦・矢矧のこの航海の乗員は450名を超える。狭く密閉した艦内で患者の隔離は不可能である。いわゆる「3密」である。ついには軍医長も倒れた。
医師・五味淵伊次郎の見聞録から考える最初の死者の最期
マニラ(1899年(明治32年))。※写真はイメージです。Licensed under public domain via Wikimedia Commons
悪病のまん延は航海にも支障をきたした。減員のため運航がままならず、重病の患者ですら高熱と苦痛を忍んで当直勤務を行った。
海上の唯一の楽しみである食事にしても悲惨だった。調理師が病に倒れ準備もままならない。海兵は自らご飯に塩を振り掛けて空腹をしのぐ以外に手はなかった。
最終的に巡洋艦・矢矧(やはぎ)は12月5日の正午マニラに到着している。しかしその前日の夜に艦内では、一等機関兵の谷広数雄が危機的な病状に陥っていた。
谷広の詳しい病状の変化は記録が残っていない。しかし後に「スペイン風邪」との戦いを記録した栃木県矢板町の医師・五味淵伊次郎の見聞録から状況は想像ができる。
スペイン風邪の患者の顔は暗く紅色の無気力な表情になる。せきが患者の安眠を妨げ、胸に浮腫が目立った。心臓まひも容易に起こり、看病者は患者に起居を許せない。
一等機関兵・谷広数雄の場合も同じだったのかもしれない。息苦しさで呼吸の回数が1分間に50回・60回に達する15。次第に呼吸が浅くなり、青紫色の顔に灰白青色や鉛色が加わる。現代のような肺炎患者に使用する人工呼吸器などこの時代、軍艦の上にはなおさらない。軍医官は手の施しようがなかった。
12月4日午後8時15分、マニラに到着する前日の夜に、真っ黒い海の上を進む巡洋艦・矢矧の艦内で、一等機関兵・谷広数雄が死んだ。シンガポール港を出た日からわずか5日目の悲劇だった。
後に、矢矧の乗組員の死者は46名に達する。この悲劇は、1年後の北陸の惨状を予告する「先触れ」に違いなかった。
しかし、当時の北陸の新聞では、遠くヨーロッパの戦況が盛んに報じられているだけで、巡洋艦・矢矧に関するニュースはない。そもそも、北陸の人たちの関心もない段階なのだ。
状況をあえて新型コロナウイルス感染症になぞられて言えばまだ、原因不明の肺炎患者が中国の武漢で現れただけのころと似ているのかもしれない。
(副編集長のコメント:次は、第2回「市中感染の第一報」に続きます。)
2軍艦の一種。遠洋航行能力・速度等を生かした攻撃力を持つ。
3三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア)と三国協商(イギリス・フランス・ロシア)を中心とした世界的な大戦争。日本は三国協商側に参加した。1918年(大正7年)11月に最後まで戦ったドイツが降伏し戦争が終わる。
4 1917年(大正6年)11月30日。
5 砲艦・最上など。
6 1917年(大正6年)11月9日。
7 1917年(大正6年)11月21日に至るまで。
8 1917年(大正6年)11月21日と22日。
9 1917年(大正6年)11月28日までに。
10 1917年(大正6年)11月30日の午後4時。
11 1917年(大正6年)12月1日。
12 1917年(大正6年)12月2日。
13 1917年(大正6年)12月3日。
14 1917年(大正6年)12月4日。
15 健康的な成人の標準的な呼吸の回数は1分間に12~20回。






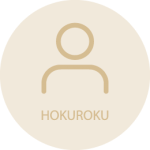






オプエド
この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。
オプエドするにはログインが必要です。